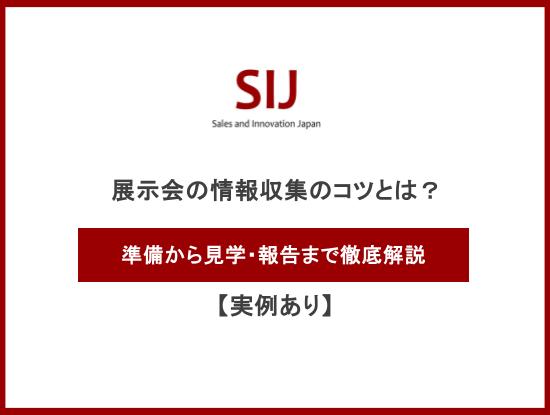展示会での情報収集は、営業部門にとって貴重な機会です。しかし、準備不足で会場を漫然と回っても、期待する成果は得られません。本記事では、展示会の情報収集を成功させるための準備から報告書作成まで、実践的なノウハウを体系的に解説します。
情報収集がうまくいかない理由
展示会に参加して情報収集を成功させるポイントは、目的を明確にして、しっかり準備をした上で、展示会に行くことです。多くの営業担当者が展示会で期待する成果を得られない理由は、事前の準備不足と明確な目的設定の欠如にあります。
展示会での情報収集に失敗する主な要因は以下の3点です。
・展示会に行く目的が曖昧
・回り方や話しかけ方がわからない
・見学後のフォローアップが不十分
これらの課題を解決するためには、体系的なアプローチが必要です。そのため、事前に「誰から」「どんな情報を得たいのか」を整理し、具体的な行動プランを立てることが重要です。
展示会に行く目的を決めよう
展示会での情報収集を成功させるためには、まず参加目的を明確に設定することが重要です。展示会の目的は下記のように分類できます。
限られた時間の中で効率的に情報収集を行うには、「新製品の動向を把握する」「競合他社の戦略を分析する」「顧客との商談に活用できる情報を収集する」など、具体的で実用的な目的を設定することが重要です。目的が明確になれば、必要な情報に絞って収集でき、見学後の報告書作成もスムーズに進められます。
展示会前の事前準備
効果的な情報収集を実現するためには、展示会当日を迎える前の準備が成功の鍵を握ります。良い報告書を書くには、見学開始前の事前準備が肝心です。報告書を提出することを念頭においてブースを回れば、後で苦労することもありません。
これらの準備を怠ると、当日になって何を見れば良いかわからず、結果として表面的な情報収集に終わってしまう可能性があります。
出展企業の調査と資料準備
展示会場に到着する前に、立ち寄る展示ブースをチェックしておきましょう。事前に立ち寄るブースをチェックしておくことで、限られた時間の中で効率よく回れます。展示会公式サイトや出展者一覧を活用して、自社の目的に合致するブースを事前に選定することが重要です。
| 調査項目 | 確認内容 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 出展企業リスト | 業界、企業規模、主力商品 | 優先度の高いブースを選定 |
| 展示内容 | 新製品、技術デモ、セミナー情報 | 質問内容の事前準備 |
| 会場レイアウト | ブース配置、動線 | 効率的な見学ルートを計画 |
メールや案内資料に記載されている注目ブースや新製品情報は必ず確認しておきましょう。これらの情報を基に、当日の見学ルートを計画することで、移動時間を最小限に抑えながら効率的に情報収集を行えます。
また、興味のある企業については、事前にWebサイトで最新情報を確認し、具体的な質問を準備しておくことで、ブースでの会話をより有意義なものにできます。
持ち物と服装の確認
展示会での情報収集を成功させるためには、適切な持ち物と服装の準備が欠かせません。動きやすい服装を選び、長時間の立ち歩きに備えた靴を着用することが基本です。
| 必需品 | 用途 | 補足 |
|---|---|---|
| 名刺 | 自己紹介、情報交換 | 1日当たり50~100枚程度 |
| メモ帳・ペン | 重要情報の記録 | デジタルツールとの併用 |
| スマートフォン | 写真撮影、連絡手段 | 充電器も必携 |
| 資料用バッグ | パンフレット収集 | A4用紙が入るサイズ |
服装については、ビジネスカジュアルが基本ですが、会社の代表として参加することを意識し、清潔感のある服装を心がけることが大切です。
ビジネスマナーの確認
展示会では初対面の方との交流が中心となるため、適切なビジネスマナーを身に付けておくことが重要です。ブースでの最初の一言が、その後の会話の質を大きく左右します。
| 基本的な話しかけ方 「気になったので、資料いただいてもよろしいですか?」 |
名刺交換は必ずビジネスマナーに従って行い、相手の話を聞く姿勢を示すことが重要です。また、ブースで説明を受けた後は、「貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」といった感謝の言葉を忘れずに伝えましょう。
展示会の情報収集を成功へ導くコツ6選
展示会での情報収集を成功させるためには、戦略的なアプローチが必要です。限られた時間の中で質の高い情報を効率的に収集するためのポイントを6つご紹介します。
①目的を1つに絞る
展示会での情報収集を成功させるためには、参加目的を1つに絞ることが重要です。
目的を絞れない場合は下記のどれかに絞りましょう。
| ・新製品の情報収集 ・競合他社の動向調査 ・顧客開拓のための情報収集 |
目的を絞ることで、必要な情報を効率的に収集できるだけでなく、見学後の報告書作成もスムーズに進められます。また、同行者がいる場合は、役割分担を明確にして情報収集の効率を高めることも可能です。
②事前にブースを選定し回るルートを決める
展示会に参加する際のどのブースをどの順番で回るかを大まかに計画しておくことは、レポートを作成する事前準備として重要です。会場マップを確認し、優先度の高いブースを中心とした効率的なルートを計画しましょう。
| ブース選定の優先度 自社の課題解決に直結>業界トレンドに関連>興味はあるが緊急度低 |
効率的なルート設定により、移動時間を最小限に抑えながら、重要な情報を漏れなく収集できます。また、人気の高いブースは混雑が予想されるため、開場直後や昼休み明けなど、比較的空いている時間帯を狙うことも重要です。
MAPの例(マーケティングWeek2025/6/18-6/20)
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html
ルート計画の際は、会場の構造や出入口の位置も考慮し、効率的な動線を設計することで、疲労を最小限に抑えながら多くの情報を収集できます。
③質問は3つだけ用意する
各ブースで聞く質問を事前に3つに絞っておくことで、会話を効率化し、聞き逃しを防ぐことができます。質問を準備しておくことで、限られた時間の中で必要な情報を確実に収集できます。
| 基本的な質問例(具体的で実践的な内容) ・「この製品の特徴は何ですか?」・「競合他社との違いは何ですか?」・「導入時の留意点は何ですか?」 |
質問を絞ることで、相手の説明をより集中して聞くことができ、その後の質疑応答もスムーズに進められます。また、時間の制約がある中で、必要な情報を効率的に収集できるメリットもあります。
④1ブース10分で切り上げる
各ブースでの滞在時間を10分程度に設定することで、多くのブースを効率的に回ることができます。10分という時間設定は、基本的な製品説明を聞き、質問を行い、資料を収集するのに適切な時間です。
この数値の根拠は以下です。
| (滞在時間(分)-全体の移動・資料整理・休憩時間(分))÷回りたいブース数 =1ブースあたりの平均時間(分) 滞在時間3時間の場合(180-60)÷12=10 |
ただし、特に重要なブースや詳細な技術説明が必要な場合は、柔軟に時間を調整することも必要です。全体のスケジュールを考慮しながら、効率的な時間配分を心がけましょう。
⑤パンフ+ひとことメモをセットで残す
各ブースで収集したパンフレットには、必ず簡潔なメモを付けておくことが重要です。具体的な情報を記録しておくことで、後の振り返りが効率的になります。
| 記録項目 | 内容例 |
|---|---|
| 担当者名 | 山田太郎様 |
| 特徴・強み | 処理速度が従来比3倍 |
| 価格・条件 | 月額10万円から |
| 印象・所感 | 操作性が良い |
メモは簡潔に要点をまとめ、後で読み返した際に内容を思い出せる程度の情報を記録しておけば十分です。デジタルツールを活用する場合は、スマートフォンの音声メモ機能を使うことも効果的です。
⑥気になったブースは2回立ち寄る
特に興味のあるブースや重要な情報を提供してくれるブースには、時間を空けて2回立ち寄ることをおすすめします。最初の訪問で基本情報を収集し、他のブースを回った後に再度訪問することで、比較検討の材料が増えます。
2回目の訪問では、他社との比較や具体的な導入条件について、より深い質問を行うことができます。また、担当者との関係性も深まり、より詳細な情報を得られる可能性があります。
| このような会話をして関係性を深める会話の例 ・「資料をもとに社内で検討したいので、追加の資料やサポートをお願いできますか?」 ・「前にお話しいただいた内容について、もう少し詳しく教えていただけますか?」 ・「私たちの希望に合わせた対応は可能でしょうか?」 |
ただし、2回目の訪問は時間的な制約もあるため、本当に重要なブースに限定することが重要です。全体のスケジュールを考慮しながら、効率的な情報収集を心がけましょう。
優先ブースの選び方と順番
展示会での効率的な情報収集を実現するためには、興味のあるブースを3〜5社程度に絞り、「回る順番」を事前に決めておくことが重要です。限られた時間で効率よく展示会を回るためには、事前準備がなにより大切なのです。
情報収集の目的で選ぶ
目的が明確になっていれば、多数のブースの中から本当に必要な情報を提供してくれるブースを効率的に選別できます。また、目的に合致しないブースは思い切って除外することで、時間を有効活用できます。
| ブース選定は、事前に設定した情報収集の目的と合致するかどうかを基準にしましょう。 ・「新製品の市場動向を把握したい」 ・「競合他社の戦略を分析したい」 ・「顧客提案に活用できる情報を収集したい」 など、具体的な目的に基づいて選定しましょう。 |
情報収集の目的と各ブースの展示内容を照らし合わせ、最も価値のある情報を得られそうなブースを優先的に選定することが重要です。
業界トレンドを優先する
最新技術や話題のサービスを展示しているブースは、業界の今後の方向性を把握する上で重要な情報源となります。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)や人工知能(AI)関連の技術は、多くの業界で注目されています。
業界トレンドを把握するためには、業界誌や専門メディアで事前に話題になっている企業や技術をチェックしておくことが効果的です。また、展示会の主催者が発表する「注目ブース」や「新製品発表」情報も参考になります。
トレンドを追うことで、自社の今後の戦略立案に役立つ情報を収集できるだけでなく、顧客との商談においても話題性のある情報を提供できるようになります。
自社の課題解決につながるブースを優先する
自社が現在抱えている課題の解決に直結する可能性があるブースは、最優先で訪問すべきです。「営業効率の向上」「コスト削減」「品質向上」など、具体的な課題解決につながる製品やサービスを展示している企業を重点的に選定しましょう。
課題解決型のブース選定では、事前に自社の課題を明確に整理し、それに対応する解決策を提供している企業を調査することが重要です。自社の課題解決に直結する情報は、展示会後の社内での価値が高く、具体的な提案や改善策の検討につながりやすいというメリットがあります。
招待状・メール案内で選ぶ
展示会の主催者や出展企業から送付される招待状やメール案内には、注目すべきブースや新製品情報が記載されています。事前に送付される資料を見落とさないよう、展示会参加が決まった段階で、関連する情報を整理・管理するシステムを構築しておくことが重要です。
DX総合EXPO2025東京【夏】2025/7/23-7/25
https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo
マーケティングWeek2025/6/18-6/20
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html
招待状に記載されている企業は、主催者が特に注目している企業である可能性が高く、業界動向を把握する上で価値のある情報を提供してくれることが期待できます。また、新製品発表や技術デモンストレーションの情報も重要な選定基準となります。
会場マップの導線で選ぶ
効率的な情報収集を実現するためには、会場マップを活用した導線設計が不可欠です。無駄な移動を減らし、限られた時間内で多くの情報を収集するために、ブースの配置を考慮した見学順序を計画しましょう。
MAPの例(マーケティングWeek2025/6/18-6/20)
https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html
| 導線設計のポイント | 効果 | 留意点 |
|---|---|---|
| 入口からの距離 | 移動時間短縮 | 混雑状況も考慮 |
| ブース間の距離 | 疲労軽減 | 優先度とのバランス |
| 人気ブースの位置 | 待ち時間削減 | 時間帯の調整が必要 |
会場マップを事前に確認し、効率的な動線を設計することで、移動時間を最小限に抑えながら、質の高い情報収集が可能になります。また、混雑が予想される人気ブースは、開場直後や昼休み時間帯など、比較的空いている時間を狙うことも重要です。
導線設計においては、優先度の高いブースから順番に回り、時間に余裕があれば興味のある他のブースも訪問するという柔軟なアプローチが効果的です。
見学レポートテンプレート【例文付き】
展示会での情報収集を最大限に活用するためには、見学後の報告書作成が重要です。報告書のテンプレートを事前に準備しておくことで、見学中に必要な情報を意識的に収集でき、後の作業効率も大幅に向上します。
学生の場合のテンプレート
学生の場合は、単純な情報収集にとどまらず、展示会で得た情報を自分の専門分野や将来のキャリアとどのように関連付けるかを考察することが重要です。また、企業の採用担当者との名刺交換があった場合は、その記録も忘れずに残しておきましょう。
学生が実習や授業レポート用に使用できるテンプレートでは、学習目的に応じた情報整理が重要です。業界理解や就職活動に役立つ情報を中心に構成することで、教育効果を高めることができます。
テンプレートは以下からご使用ください。
【Sales and Innovation Japan】展示会見学レポート(学生)(コピーで作成よりご活用ください)
左上、「ファイル」からコピーを作成でご活用ください。
また、以下入力例となります。こちらをご参照の上ご作成ください。
新人社員の場合のテンプレート
新人社員が社内共有や上司報告にそのまま使える報告書テンプレートでは、実務的な観点からの情報整理が求められます。自社の事業に与える影響や今後の対応方針についても触れることが重要です。
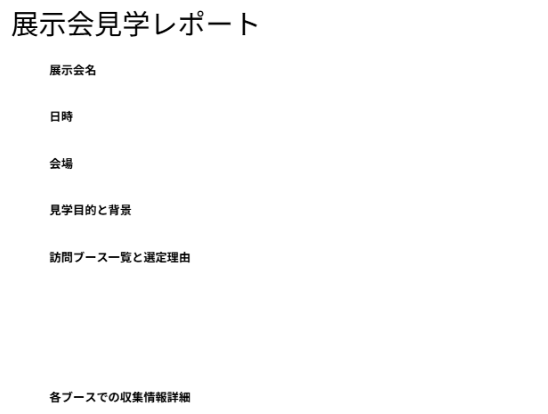
テンプレートは以下からご使用ください。
【Sales and Innovation Japan】展示会見学レポート(新入社員)(コピーで作成よりご活用ください)
左上、「ファイル」からコピーを作成でご活用ください。
また、以下入力例となります。こちらをご参照の上ご作成ください。
新人社員の場合は、展示会で得た情報を自社の現状や課題と照らし合わせて分析し、具体的な改善提案や今後の検討事項を明確にすることが重要です。また、上司や関係部署との情報共有を前提とした、読みやすく分かりやすい文章を心がけましょう。
パワーポイントでまとめる場合のテンプレート
口頭報告や会議資料として使用するパワーポイントテンプレートでは、視覚的な分かりやすさと要点の整理が重要です。限られた時間内で効果的に情報を伝える構成を心がけましょう。
テンプレートは以下からご使用ください。
【Sales and Innovation Japan】パワーポイントでまとめる場合(コピーで作成よりご活用ください)
左上、「ファイル」からコピーを作成でご活用ください。
パワーポイントでは、テキストだけでなく、会場で撮影した写真や収集した資料の画像を効果的に活用することで、臨場感のある報告が可能になります。また、各スライドには結論を明確に示し、聞き手が理解しやすい構成にすることが重要です。
展示会でありがちな失敗
展示会での情報収集において、多くの参加者が犯しがちな失敗パターンを理解し、事前に対策を講じることが成功の鍵となります。特に、事前準備の重要性を理解し、計画的にアプローチすることが重要です。
目的が曖昧なまま参加
展示会参加の目的が曖昧なまま会場に向かうと、何を見るべきかが分からず、ブースをただ眺めるだけで終わってしまいがちです。このような状況では、せっかく時間をかけて参加しても、得られる情報は表面的なものに留まってしまいます。
| 展示会参加前に明確にすべきこと 1「何のために行くのか」 2「どのような情報を得たいのか」 |
目的が明確になれば、必要な情報に集中でき、効果的な情報収集が可能になります。
話すだけで記録しない
展示会のブースで担当者と話をして満足してしまい、重要な情報をメモに残さないケースが多く見られます。その場の会話では理解できたつもりでも、時間が経つと詳細な内容を思い出せなくなってしまいます。
パンフレットだけでは、担当者から聞いた具体的な条件や特徴、価格情報などの重要な情報が抜け落ちてしまいます。各ブースでの会話内容は、必ず簡潔でもメモに残し、後で活用できるようにしておくことが重要です。
全部のブースを回ろうとする
展示会場にある全てのブースを見て回ろうとすると、時間が足りず、どのブースも中途半端な情報収集で終わってしまいがちです。特に大規模な展示会では、数百社が出展していることもあり、全てを回るのは現実的ではありません。
興味のあるブースを3〜5社程度に絞り、それぞれのブースでじっくりと情報収集を行う方が、得られる情報の質が高くなります。量より質を重視したアプローチが、展示会での情報収集を成功させる鍵となります。
名刺だけ集めて放置する
展示会では多くの担当者と名刺交換を行いますが、名刺を集めるだけで満足してしまい、その後のフォローアップを怠ってしまうケースが多く見られます。名刺交換はあくまでも関係構築の入り口であり、その後の継続的なコミュニケーションが重要です。
名刺交換を行った際は、会話内容を簡潔にメモし、必要に応じて展示会後にフォローメールを送るなどの対応が重要です。このような継続的な関係構築により、展示会での情報収集の効果を最大限に活用できます。
学生や若手社員のための展示会のコツ
展示会に慣れていない学生や若手社員にとって、ブースでの適切な振る舞いや効果的な情報収集方法を身に付けることは重要です。挨拶・話しかけ方・断り方などの基本的なマナーを押さえるだけで、相手に与える印象が大きく変わります。
あいさつと話しかけ方の基本
展示会のブースで担当者に声をかける際は、適切なタイミングと方法を選ぶことが重要です。担当者が他の来場者と話している際は、少し離れた場所で待ち、会話が終わったタイミングで声をかけるのがマナーです。
| 基本的な流れとして、「興味があるので、資料をいただいてもよろしいでしょうか。」と声をかけると、相手から「良ければ、説明しましょうか?」と言われることが多いです。その後、「××について教えていただけますでしょうか」といった具体的な質問を投げかけることで、スムーズな会話に発展させることができます。 |
質問をする際は、事前に準備した3つの質問を中心に、相手の説明を聞きながら追加の質問を行うことが効果的です。また、相手の話を聞く姿勢を示すため、適切なタイミングで相槌を打ち、メモを取る姿勢を見せることも重要です。
「見るだけ」でも失礼にならない方法
展示会では、特定の購入意図がなくても情報収集のために訪問することは一般的です。「見るだけ」でも失礼にならない方法を身に付けることで、プレッシャーを感じることなく展示会を活用できます。
| ブースの担当者から声をかけられた際 ・「勉強のために拝見させていただいています」 ・「業界の動向を調べており、参考にさせていただいています」 といった形で、見学の目的を正直に伝えることが効果的。 |
関心が薄い製品やサービスの説明を受けた場合は、「貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。資料を拝見させていただきます」といった形で、丁寧に会話を終了することができます。
展示会後の印象アップにつながる行動
展示会での情報収集は、当日の活動だけでなく、その後のフォローアップが印象向上につながります。名刺交換を行った担当者には、展示会後24時間以内にお礼メールを送ることで、良い印象を与えることができます。
| お礼メールでは、「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました」という感謝の気持ちを伝え、「××について詳しく教えていただき、大変参考になりました」といった具体的な内容に触れることで、印象に残りやすくなります。 |
また、適切な範囲でのSNS投稿や学校・職場での情報共有も、展示会参加の成果を示すものとして効果的です。ただし、企業の機密情報や未発表の情報については、適切な配慮が必要です。
お礼のメールについては下記の記事で解説していますので是非ご覧ください。
マーケティング担当者の実際の行動例
今回は、当社SIJの若手マーケティング社員が実際に展示会をどのように回ったのかをご紹介します。当日の動きや感じたことを通して、情報収集の具体的なヒントをお伝えします。
当社マーケティング担当
・入社3年目
・BtoB商材のマーケティング担当
・展示会参加は今回で3回目
実際の動線・回り方
あるマーケティング担当者の実際の展示会での動線を例に、効果的な情報収集方法を解説します。開場30分前に到着し、会場マップを再確認した後、優先度の高いブースから順番に回るという基本的な流れを実践しています。
実際の動線では、会場の入口に近いブースから目星をつけていた企業のブースを効率的に回っています。また、いくつかのブースを回っては資料を整理するということを繰り返しているとのことでした。
優先ブースの選び方
まず最優先にしているのは、やはり「自社の課題解決に直結する企業」だそうです。事前に自社の状況を整理したうえで、導入の可能性があるソリューションを扱っている企業を中心にリストを作成し、当日はそこから回っていくとのことでした。
一方で、すぐに導入する予定がなくても、将来的に役立ちそうな情報が得られそうな企業については、優先度を下げて訪問対象に含めているそうです。予算的なハードルがある企業でも、今のうちに話を聞いておくことで、あとから社内で検討しやすくなると話していました。
また、現場では予定になかったブースにも立ち寄ることがあるようで、「人の流れや盛り上がりを見て、気になったら覗いてみることもある」とのこと。偶然の出会いが思わぬヒントにつながることもあるようです。
1ブースは想定より長くかかった
実際の展示会では、事前に計画した1ブース10分という時間設定が現実的でないことが多くあったそうです。特に関心度の高い企業や、説明のうまい担当者に当たった場合、つい話が盛り上がってしまい、気づいたら15分以上滞在していたというケースも珍しくなかったとのこと。
ただ、その時間延長をネガティブには捉えておらず、むしろ「深く話せたことで相手の印象に残ったり、見えてなかった課題に気づけた」という感触もあったそうです。
一方で、予定がずれ込むことは当然あるため、「残りのブースとの優先度をその場で見直しながら調整していくことが大事」とも話していました。限られた時間の中で、どこに時間をかけるべきかを現場で判断する柔軟さも必要だと感じたそうです。
また、同じ企業が別ブランドや別サービスで複数のブースを出しているケースもあり、ブース名だけで判断していると重複してしまうことがあります。知らずに同じ会社のブースを何度も訪れてしまうと、時間をロスする可能性もあるので注意が必要とのことです。
名刺交換は予定の6割に留まった
当初の計画では多くの企業と名刺交換を行う予定でしたが、実際には予定の6割程度に留まるケースが多く見られます。これは、限られた時間の中で質の高い情報収集を優先した結果であり、必ずしも失敗ではありません。
| 名刺交換 予定枚数 30枚 実際の交換枚数 18枚 |
名刺交換の数よりも、各ブースでの会話の深さや得られる情報の質を重視することで、より価値のある成果を得ることができます。表面的な名刺交換を多数行うよりも、少数の企業と深い関係を構築する方が、長期的には有効です。
当日ふらっと立ち寄ったブースが意外と◎
担当者によると、当日ふらっと立ち寄ったブースで、思いがけず有益な情報が得られることもあったそうです。予定には入れていなかったものの、担当者から積極的に声をかけられたことで話が弾み、結果的に有益な接点となったとのことです。
実際に立ち寄ってよかったと感じたのは、コンパニオンが少なく、営業担当とすぐに話せるブースでした。そうしたブースでは、短時間でも具体的な話に入りやすく、密度の濃い情報収集ができたといいます。
ただし、予定外のブースに立ち寄る場合は、全体のスケジュールを崩さないように注意が必要です。あくまで時間に余裕がある場合に限って判断するのが現実的です。
下記記事では、展示会の営業について解説していますので、是非ご覧ください。
まとめ
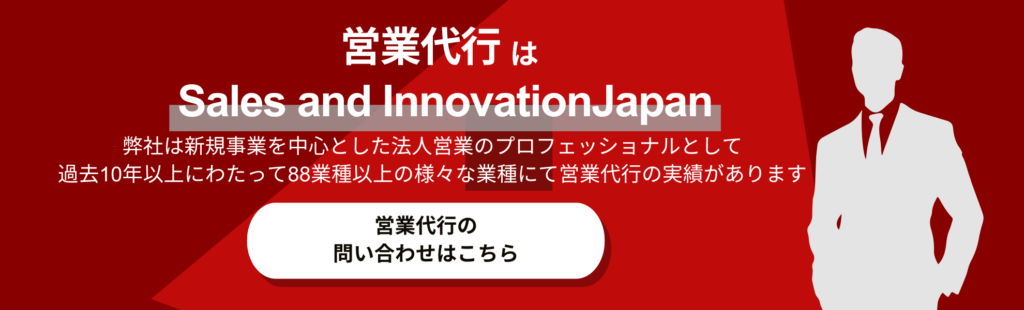
展示会での情報収集を成功させるためには、事前の準備から当日の行動、そして事後のフォローアップまで、体系的なアプローチが必要です。特に重要なのは、明確な目的設定と効率的な情報収集方法の実践です。
また、展示会は貴重な情報収集の機会です。適切な準備と戦略的なアプローチにより、営業活動やマーケティング活動に大きな価値をもたらす成果を得ることができます。今回紹介した手法を実践し、より効果的な展示会活用を目指してください。
弊社Sales and Innovation Japanは、営業に不安がある企業様をサポートし、成果を上げるお手伝いをいたします。毎月の研修を通じて、スキルアップや新たな気づきを得たい方に最適な機会を提供しています。まずは、お気軽にご相談ください。


早稲田大学卒業後、コンサルティングファームを経て、
株式会社Sales and Innovation Japanにジョイン。
大手スキマバイトアプリの営業支援や、ITシステム事業の新規事業立ち上げに従事。
現在、エンタープライズ企業向けコミュニティ“EIN”の立ち上げに奮闘。