営業活動を取り巻く環境は日々変化しており、それに伴い営業組織が抱える課題も複雑化・多様化しています。
ここでは、現場でよく見られる営業課題の具体例とその解決策を体系的に整理。さらに、自社の課題を見つけるための視点や、将来的に直面する可能性のある課題まで網羅的に解説します。
営業課題とは何か?
営業課題とは、営業活動において目標達成を阻害する要因のことを指します。
例えば、「売上が上がらない」「新規顧客の開拓が進まない」「営業担当者のモチベーションが低い」といった現象は、すべて営業課題の一例です。
営業課題を放置すると、短期的には成果の悪化、長期的には組織全体の競争力低下につながります。したがって、営業課題を早期に発見し、適切に対処することが重要です。
なぜ営業課題が発生するのか
営業課題の原因は多岐にわたりますが、主に以下のような要因が挙げられます。
- 組織設計や人材配置が適切でない
- 教育・育成が機能していない
- 営業プロセスが整備されていない
- 評価制度やマネジメントに問題がある
- 顧客ニーズや市場環境の変化に対応できていない
- データ活用やツール導入が不十分
- 組織文化や連携体制に課題がある
このように、営業課題は単一の要因ではなく、複数の問題が複雑に絡み合って発生するケースが大半です。そのため、表面的な現象だけでなく、根本原因を見極めて対処することが求められます。
よくある営業課題とその解決方法
営業組織には、売上が伸びない、顧客アプローチが不足している、営業スキルが属人的で再現性がないといった課題が頻出します。
これらの課題は、組織の成長を妨げる要因となり得るため、早期の発見と対処が重要です。ここでは、営業現場でよく見られる代表的な課題と、その具体的な解決方法について解説します。
- 組織体制に関する課題
- 人材・育成に関する課題
- 営業プロセスに関する課題
- マネジメント・評価に関する課題
- 戦略・方針に関する課題
- ツール・データ活用に関する課題
- 組織文化・風土に関する課題
- 外部環境に関する課題
組織体制に関する課題
営業組織の成果は、組織体制と役割分担に大きく左右されます。
ですが実際には、属人化や責任の曖昧さ、非効率な担当割り振りなど、体制に起因する課題が多くの現場で見受けられます。
- 役割分担が曖昧で、業務が属人化している
- インサイドセールスやCSとの連携が弱い
- 組織再編後に営業の責任範囲が不明確になっている
- 担当の割り振りに偏りがあり、非効率が生じている
- 意思決定のプロセスが複雑で対応が遅れやすい
役割分担が曖昧で、業務が属人化している
営業現場において、誰が何を担当するかが明確でない状態は、組織運営に多くのリスクをもたらします。
■ 問題点
- 特定の営業担当者に業務が集中し、担当者の不在時に業務がストップ
- 営業ノウハウが個人にとどまり、組織全体に展開できない
- 成果や進捗が可視化されず、マネジメントが困難に
■ 原因・要因
- 営業プロセスや業務範囲の定義が曖昧
- 情報共有の仕組みやツールが未整備/未活用
- 少人数・急成長の組織では、体制整備が後回しになりやすい
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| 業務の役割分担を明確化 | 「アポ取得」「商談」「提案」などを業務単位で定義し、担当者を割り当てる |
| 営業支援ツール(SFA・CRM)の導入/活用 | 顧客情報・商談進捗を組織で一元管理し、属人化を回避 |
| ナレッジ共有体制の構築 | ペア営業やローテーションで、複数人が対応できる体制に |
営業の属人化を解消するには、役割の明確化やナレッジ共有が不可欠です。
「どこから手を付ければいいかわからない…」という方は、こちらの記事で営業組織の設計ポイントを詳しく解説しています。
営業組織の体制とは?理想の組織作りから具体的な整え方まで完全解説
インサイドセールスやCSとの連携が弱い
インサイドセールスやカスタマーサクセス(CS)との連携が不十分だと、営業活動が分断され、リード管理や顧客対応の精度が落ちやすくなります。情報の共有不足は顧客満足度の低下にも直結するため、部門間の連携体制の整備が重要です。
なお、「インサイドセールスとMAを連携させ、有効商談数が週10件→50件へ5倍、商談率も2.5倍に向上した事例」(パーソルプロセス&テクノロジー,“事例”,,https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/case/marketingautomation_01/)や、「ホットリード抽出自動化で商談化件数20倍、ヒアリング工数10分の1削減の事例」(9E,“事例”,9E INSIDE SALES MEDIA,不明,https://9e-career-insidesales.com/articles/column/knowledge/89)も報告されています。
■ 問題点
- 情報共有が不十分で、リード対応や引き継ぎに漏れが生じる
- 顧客対応が断片化し、顧客体験の質が低下する
- CSで得られた情報や声が営業に活かされず、提案の質が上がらない
■ 原因・要因
- インサイドセールス、CS、営業それぞれが別々のKPIを追っている
- 定例ミーティングやチャットなど、連携のための仕組みがない
- リード管理や顧客履歴がExcelや個人メモなどで属人化している
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| 共通KPI・指標の設定 | インサイドセールス・営業・CSで連携しやすい目標を設け、連携を促進 |
| 定期的な連携ミーティングの実施 | 案件状況・顧客情報の認識をすり合わせ、リードの取りこぼしを防止 |
| SFA・CRMの共通運用 | 顧客接点の履歴を全体で可視化し、スムーズな引き継ぎと提案につなげる |
インサイドセールスやCSとの連携が弱いと、リード対応の漏れや提案の質低下を招きます。情報の分断を防ぐには、SFAなどを活用した連携体制の構築が不可欠です。詳しくは事例付きで解説したこちらの記事をご覧ください。
インサイドセールス代行18選徹底比較!強み・業界別で4タイプに分類して紹介
組織再編後に営業の責任範囲が不明確になっている
組織改編や事業再編が行われた後、営業部門における業務範囲や責任の所在があいまいになるケースは少なくありません。こうした状態が長引くと、営業活動の混乱や成果の停滞につながるため、早急な明確化と再設計が求められます。
■ 問題点
- 営業プロセスにおけるタスクの抜け漏れや重複が発生する
- メンバー間での業務押し付け合いや責任のなすりつけが起こる
- 顧客対応が不安定になり、信頼を失いやすくなる
- マネジメント層が正確な進捗把握や成果評価を行いにくくなる
■ 要因・原因
- 組織再編時に営業業務の棚卸しが十分に行われていない
- 部門間の連携設計がされておらず、役割が曖昧なまま
- 上層部が営業現場の実情を把握できていない
- 権限移譲のルールが曖昧で、個人依存の状態が継続している
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 業務範囲が曖昧で混乱している | 営業業務の全体フローを可視化する | 誰がどのタイミングで何を行うか、業務の流れを明文化して共有 |
| 担当者ごとの業務が属人化している | RACIマトリクスを用いて役割定義を明確化 | 「責任者」「実行者」「協力者」「報告先」を明確に分ける |
| 部門間の連携が機能していない | インサイドセールスやマーケとの合同会議を定期開催 | 情報連携と課題共有の場を設け、相互理解と協力体制を築く |
| 現場への周知が不十分 | 業務ルールをガイドライン化し、全員に周知徹底 | ドキュメント化し、定期的にアップデート・確認の場を設ける |
担当の割り振りに偏りがあり、非効率が生じている
営業組織内での担当割り振りに偏りがあると、特定のメンバーに業務が集中し、過剰な負荷がかかったり、逆に一部の人材が十分に活用されない状況が生じます。こうした非効率は、成果のバラつきや組織全体のモチベーション低下にもつながるため、早期の是正が必要です。
■ 問題点
- 一部の営業担当に業務や案件が集中し、過重労働・モチベーション低下を招く
- 他のメンバーの稼働率が低下し、組織全体の生産性が落ちる
- 得意領域やスキルが活かされず、成果の最大化ができない
- 顧客対応の品質に差が生じ、信頼を損なう可能性がある
■ 要因・原因
- 担当割り振りが「属人的な判断」に基づいて行われている
- 各メンバーのスキル・案件状況を可視化できていない
- 定期的な業務バランスの見直し体制がない
- 組織的なKPI設定がなく、個人単位での最適化に留まっている
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 業務が一部の人に偏っている | 業務配分のモニタリングと定期的な棚卸しを実施 | 稼働状況や案件数を可視化し、バランスのとれた配分を行う |
| スキルに合わない業務を割り振っている | メンバーごとの得意領域や経験をデータベース化 | 適材適所の観点で割り振りを行い、成果と満足度を高める |
| 担当配分が不透明で不満が生じている | 担当決定の基準をルール化し、透明性を確保 | 割り振りの根拠を明文化することで、納得感と公平性を担保 |
| 業務量の見直しがされない | 定例会議で業務量の状況を確認し、見直しを促す | チーム内での共有・調整を習慣化することで、偏りを未然に防ぐ |
意思決定のプロセスが複雑で対応が遅れやすい
営業の現場では、スピードが結果を左右します。しかし、意思決定に関わるプロセスが複雑すぎると、現場での柔軟な対応ができず、貴重なビジネスチャンスを逃すリスクが高まります。
特に、提案内容の変更や価格の調整、例外対応など、迅速な判断が求められる場面でボトルネックになりやすい課題です。実際、経済産業省の調査(2022年)によれば、デジタル化の遅れや意思決定プロセスの複雑さが原因で、約50%以上の企業が業務効率の低下を課題と認識しており、これが営業対応の遅れや機会損失にも直結していることが示されています(経済産業省,“DXレポート2.2(DX実現に向けた課題と対応)”2022,https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf,2025/7/5)。
■ 問題点
- 商談中の即時対応ができず、競合に後れを取る
- 顧客対応のスピードが落ち、満足度が低下する
- 承認待ちで営業担当の業務が停滞する
- 現場の判断権限が乏しく、モチベーション低下につながる
■ 要因・原因
- 承認者が多く、意思決定までに時間がかかる
- ルールや判断基準が曖昧で、逐一確認が必要
- 権限移譲が進んでおらず、現場に裁量がない
- 部門間の連携不足により調整に手間取る
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 承認フローが煩雑 | 承認プロセスの段階を簡素化 | 重要度に応じた承認ルートを設定し、不要な承認を削減 |
| 判断に時間がかかる | 判断基準の明文化・ルール整備 | よくあるケースをガイドライン化し、現場の判断力を強化 |
| 現場の裁量が乏しい | 権限委譲の範囲を明確化 | 現場で判断できる領域を広げ、対応スピードを向上 |
| 部門間調整が遅い | 営業・CS・マーケの連携体制強化 | 定例会や窓口統一により、横断的な調整をスムーズに |
人材・育成に関する課題
営業組織の成長には、優れた人材の確保と継続的な育成が欠かせません。
しかし実際には、若手の育成不足やベテランとの成果の格差、教育施策の形骸化など、さまざまな人材課題が浮き彫りになっています。 これらの課題を放置すると、組織全体のパフォーマンスや定着率にも悪影響を及ぼしかねません。人材戦略と育成の在り方を見直すことが、営業力強化の第一歩となります。
- 若手のスキルが不足しており成果が安定しない
- ベテランと若手で行動量・成果に差がある
- 優秀な営業の離職が多く、定着しにくい
- マネージャーが育成に時間を割けていない
- 教育施策(OJT・ロープレ等)が形骸化している
若手のスキルが不足しており成果が安定しない
営業組織において、若手社員の成長は組織全体のパフォーマンスに直結します。
しかし、経験や知識が不足している若手が即戦力として成果を出すには限界があり、**放置すれば成果のばらつきやチーム全体の足並みの乱れにもつながります。**育成と支援の仕組みを整えることが重要です。
■ 問題点
- 成果に個人差が出て、組織全体の目標が達成しづらい
- 若手のモチベーションが低下し、離職リスクが高まる
- ベテランに負担が集中し、組織の生産性が下がる
- ノウハウが属人化し、再現性のある営業活動ができない
■ 要因・原因
- 体系的な研修やOJTが整っていない
- フィードバックの仕組みがなく、改善が難しい
- ベテランの暗黙知が共有されていない
- 若手自身が「何ができていないか」を把握できていない=
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| スキルのばらつき | 研修プログラムの標準化と定期実施 | トーク・資料作成・CRM操作などを体系的に学べる研修を整備 |
| ノウハウの属人化 | ベテランの知見をドキュメント化・共有 | 商談成功パターンをマニュアルやケーススタディに落とし込む |
| 改善の機会がない | 定期的なロールプレイ・レビュー会の実施 | 上司や先輩からの具体的なフィードバック機会をつくる |
| 若手の成長が遅い | メンター制度の導入 | 経験豊富な社員がフォロー役となり、日々の悩みをサポート |
若手営業のスキル不足は、成果のばらつきや離職リスクを招き、組織全体の生産性低下につながります。属人化の解消や育成体制の整備が急務です。体系的な支援体制の整え方を、具体例を交えて解説したこちらの記事をご覧ください。
ベテランと若手で行動量・成果に差がある
営業組織において、ベテランと若手の間で行動量や成果に大きな差が出るケースは珍しくありません。
この差が放置されると、若手の成長が停滞し、組織の将来性にも悪影響を与えかねません。属人的な営業から脱却し、全体の底上げを図る仕組みが求められます。
■ 問題点
- 若手の成果が安定せず、個人任せの営業に依存してしまう
- 成果や行動量に差があることで、チーム全体の士気が下がる
- 若手が早期に自信を失い、モチベーション低下・離職につながる
- ベテランのノウハウが属人化し、ナレッジが蓄積・共有されない
■ 要因・原因
- 若手が営業プロセスを体系的に理解できていない
- 経験やスキルの違いにより、同じ目標設定が不公平に感じられる
- ベテランの業務がブラックボックス化しており、若手の学習機会が乏しい
- 行動量や努力を評価する仕組みが整備されていない
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 若手の成果が伸び悩む | 営業プロセスの分解とマニュアル化 | ベテランの成功事例を明文化し、再現可能な手順を提示する |
| 組織内で行動量にバラつきがある | 行動KPIの設計とダッシュボード共有 | 架電数・訪問数など行動指標を可視化し、日々の行動改善を促す |
| 若手のモチベーション低下 | フィードバック文化と育成支援の強化 | 定期的な1on1やフィードバックで成長実感を得られる環境をつくる |
| ベテラン依存の属人化 | ナレッジシェアの仕組みを構築 | ロープレ、勉強会、動画共有などでベテランの技術を若手に伝える |
優秀な営業の離職が多く、定着しにくい
「営業職は全職種平均の15.4%を超える離職率を示し、業界によっては20%以上に達する場合もあり、特に若手や新規開拓を担う層で離職リスクが高い」(DIGIMA,“営業職の離職率に関する調査”,Sales Hacks,不明,https://saleshacks.digima.com/,2025/7/4)と指摘されており、営業人材の離職は売上低下だけでなく、育成コストや組織モチベーションにも影響します。
成果を出している営業人材の離職が続くと、短期的な売上減少にとどまらず、育成コストやチーム全体のモチベーションにも大きな影響を及ぼします。
営業組織の持続的な成長には、優秀な人材が安心して働き続けられる環境づくりが不可欠です。
■ 問題点
- 営業成績の中核を担っていた人材が抜け、売上が落ち込む
- 採用や教育コストがかさみ、非効率な人員サイクルが続く
- 残ったメンバーの業務負荷が増し、さらなる離職を招く
- ノウハウや人脈が社内に蓄積されず、組織としての成長が止まる
■ 要因・原因
- 優秀な人材への評価・報酬が不十分で、やりがいを感じにくい
- キャリアパスや役割の明示がなく、成長イメージが描けない
- マネジメント層との信頼関係が薄く、課題が表面化しにくい
- 成果を出す人ほど業務が偏り、過重労働になりやすい
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 離職による売上の急落 | 成果に連動した報酬制度の見直し | インセンティブや昇進の透明性を高め、貢献度に報いる仕組みを整備 |
| 優秀人材のやりがい不足 | キャリアパスや専門性育成の設計 | マネジメント、スペシャリストなど多様な道を示し、将来像を具体化 |
| 信頼関係の希薄化 | 定期的な1on1や360度評価の導入 | 上司・同僚との関係性を強化し、問題を早期発見・対応する体制を構築 |
| 過重労働による疲弊 | タスク配分の見直しと属人化の排除 | 業務の棚卸と平準化を図り、ベテランへの業務集中を回避する |
マネージャーが育成に時間を割けていない
営業マネージャーが数値管理や現場対応に追われ、部下の育成に十分な時間を取れていない状況は多くの組織で見られます。
育成が後回しになることで、若手の成長が停滞し、チーム全体の成果にばらつきが生まれやすくなります。
■ 問題点
- 若手や中堅の営業が育たず、常に属人的な営業体制に依存してしまう
- スキルの底上げが進まず、組織の生産性が頭打ちになる
- マネージャーに業務が集中し、離職リスクが高まる
- 育成不十分による失注やクレームが増加する
■ 要因・原因
- マネージャーがプレイングマネージャー化しており、稼働時間の大半を実務が占めている
- 育成に関する仕組みやノウハウが整備されていない
- トレーニングやOJTが属人的で、効率化されていない
- 育成が「緊急ではない業務」として後回しにされがち
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 育成時間の不足 | マネージャー業務の一部委譲・分担 | 営業支援担当やサブマネージャーの設置で負担を軽減し、育成時間を確保 |
| 属人的な育成 | 育成用のマニュアル・トレーニング体系の整備 | 教える内容を標準化し、誰が指導しても一定の成果が出る仕組みを作る |
| OJT依存の非効率さ | 定期的な研修・ロールプレイを導入 | 計画的・体系的なスキルアップを実現する場を用意 |
| マネージャーのリソース不足 | KPIや会議運営の自動化・効率化 | ダッシュボードやレポートツールで業務を効率化し、育成への投資時間を捻出 |
教育施策(OJT・ロープレ等)が形骸化している
営業メンバーの育成を目的に導入されたOJTやロールプレイングなどの教育施策も、継続的な見直しや運用が伴わなければ、やがて“やること自体”が目的化してしまいます。
形骸化した教育はスキル向上に寄与せず、時間の浪費にもなりかねません。
■ 問題点
- 実施することが目的となり、スキル向上につながっていない
- フィードバックが形だけで、メンバーに定着しない
- 成長実感を得られず、モチベーションが下がる
- 教育効果が不明確なため、育成計画の改善が難しい
■ 要因・原因
- 目的や評価基準が明確でないまま運用されている
- 内容が実務に即しておらず、現場で活かせない
- フィードバックが属人化・感覚的で一貫性がない
- 運用負荷が高く、形だけの実施になっている
■ 解決策
| 課題 | 解決策 | 解説 |
|---|---|---|
| 教育施策の目的不明確 | OJTやロープレの「目的」「ゴール」「評価項目」を明文化 | なぜ行うのか、どこまでできればOKかを明示し、実施の意味を共有する |
| 実務との乖離 | ロープレ内容を実際の商談や架電内容に即して設計 | 実業務に近い形で訓練することで、即時的な改善効果を狙う |
| フィードバックの属人化 | 評価シートやチェックリストを導入し、統一指標で振り返り | 誰が指導しても一定の基準で評価できるようにする |
| 継続運用の負荷 | 実施スケジュールや工数をマネージャーが把握・設計 | 回数や負担を調整しながら、継続できる仕組みを整える |
OJTやロープレが「やること自体が目的」になっていませんか?教育施策が形骸化すると、スキルは伸びず、現場も疲弊します。営業育成の“あるある課題”と、その打開策を整理した実践記事はこちらの記事をご覧ください。
営業プロセスに関する課題
営業成果を安定して上げ続けるためには、明確なプロセス設計とその適切な運用が不可欠です。しかし現場では、「どの段階で何をすべきか」が曖昧だったり、プロセスが機能せず属人的な動きに頼ってしまっているケースも少なくありません。営業活動のムラや成果のばらつきが目立つ場合、営業プロセスの設計や運用に何らかの課題が潜んでいる可能性があります。
- 案件の管理方法が人によってバラバラ
- 顧客情報の管理がExcel中心で属人化している
- フォロー対応のタイミングが場当たり的で失注が多い
- リード対応が遅く、機会損失が起きている
- クロージングまでの流れに再現性がない
案件の管理方法が人によってバラバラ
営業担当者ごとに案件管理のやり方が異なると、組織としての情報の一元化や共有が難しくなります。進捗の把握やフォロー体制が属人化し、結果的に失注リスクの見落としや引き継ぎミスにつながる可能性も高まります。
このような状態では、営業活動の最適化や再現性のある成果創出が難しくなります。
■ 問題点
- 営業活動の進捗や状況が可視化されず、マネジメントが困難
- 情報が個人に閉じており、チームとしての連携が取りづらい
- 引き継ぎやフォローが属人化し、対応ミスが発生しやすい
- 成果につながる営業プロセスの再現ができない
■ 要因・原因
- 案件管理のルールやフォーマットが定まっていない
- CRMやSFAが導入されていない、または活用されていない
- 管理の目的やメリットが現場に伝わっていない
- 個々の営業のやり方に任せきりで、統制が取れていない
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| 案件管理の統一ルール策定 | ステータス定義、入力項目、管理粒度などを標準化 |
| CRM・SFAの導入・活用推進 | 一元管理・自動連携により、属人的な運用を回避 |
| 利用マニュアル・研修の実施 | ツールの使い方や活用事例を共有し、浸透を図る |
| KPIに管理精度を組み込む | 案件管理の質を評価項目に含め、習慣化を促進 |
| 定期的なレビュー・棚卸し | 管理状況を可視化し、抜け漏れを防止する体制を整備 |
案件管理のやり方が人によってバラバラ…そんな状況は、営業組織の非効率や失注リスクの温床になりかねません。管理の属人化を防ぎ、再現性ある営業体制を築くポイントを解説した記事はこちらの記事をご覧ください。
顧客情報の管理がExcel中心で属人化している
顧客情報の管理をExcelで行っている場合、情報の更新漏れや重複、共有の不備といった問題が起こりやすくなります。
特に担当者個人のPC上に保存されている場合は、他メンバーが情報を把握できず、組織全体の営業効率を下げる要因となります。こうした属人的な管理体制は、営業の引き継ぎ・分析・改善を困難にし、成約率の低下や顧客満足度の低下にもつながりかねません。
■ 問題点
- 情報更新が手動で、最新状態を保ちにくい
- 情報が個人単位で管理され、共有・引き継ぎが困難
- 顧客データの重複や漏れが起こりやすい
- 分析やセグメント配信などの活用が難しい
■ 要因・原因
- Excel管理が慣習化しており、見直しが行われていない
- CRMなどのツール導入が進んでいない、あるいは現場で活用されていない
- 情報管理の目的や活用方法が組織で共有されていない
- データ整理の手間や学習コストへの懸念がある
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| CRMの導入と標準化 | 顧客情報を一元管理し、リアルタイムに更新・共有可能な環境を整備 |
| 顧客管理ルールの策定 | 入力項目や更新タイミングを統一し、精度と効率を向上 |
| 現場向けマニュアルの作成 | CRMの操作手順や活用事例を整理し、属人性を排除 |
| 定期的なデータクレンジング | 不要なデータや重複情報の整理を定期的に実施 |
| データ活用の成果を可視化 | 分析や施策成功例を共有し、活用意識を高める |
フォロー対応のタイミングが場当たり的で失注が多い
顧客へのフォローアップが個人の判断や感覚に任されていると、適切なタイミングでのアプローチができず、興味関心が高い見込み客を取りこぼしてしまうというリスクがあります。
場当たり的な対応は、営業活動の再現性を損ない、組織としての受注率向上にもつながりにくくなります。
■ 問題点
- フォローのタイミングが営業個人に依存しておりバラつきがある
- 顧客ニーズが高まっている時期にアプローチできていない
- 見込み顧客の優先度が適切に管理されていない
- 営業活動の再現性が低く、ナレッジが蓄積されにくい
■ 要因・原因
- フォローの基準やタイミングが明文化されていない
- CRMなどで顧客の状態やアクション履歴を可視化できていない
- 案件管理が属人的で、情報共有が不十分
- リマインドやアラートの仕組みがなく、対応が後手に回る
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| フォローアップ基準の明確化 | 顧客の行動やステージに応じた対応ルールを定め、営業全体で統一 |
| CRMを活用したアクション管理 | 顧客の反応や接触履歴を一元管理し、適切なタイミングを見極める |
| リマインダー・アラート機能の活用 | 次回アクションを自動で通知し、フォロー漏れを防止 |
| ナーチャリングシナリオの設計 | メールや架電のタイミングを自動化・半自動化して失注を防ぐ |
| 属人管理の排除と共有体制の構築 | チーム全体で案件進捗を共有し、フォローの抜け漏れを防止 |
リード対応が遅く、機会損失が起きている
資料請求や問い合わせといった顕在化したリードに対する初動対応が遅れると、競合に先を越されたり、顧客の興味関心が冷めたりする可能性があります。スピード感のない対応は、せっかく獲得したリードの取りこぼし=機会損失につながるため、営業組織にとって致命的な課題になりかねません。
■ 問題点
- 問い合わせや資料請求への初回対応に時間がかかっている
- 顧客の温度感が高いうちにアプローチできず、競合に流れている
- リード対応が営業担当の工数や判断に依存してしまっている
- マーケティング部門と営業部門の連携が不十分
■ 要因・原因
- インバウンドリードの通知やエスカレーションが遅い
- リード割り振りや対応ルールが整備されていない
- 営業担当が他業務で手一杯で、即時対応が難しい
- MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRMの活用が不十分
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| 初動対応時間のKPI化 | 問い合わせから初回アクションまでのリードタイムを指標として管理する |
| インバウンド対応ルールの整備 | 担当アサインや対応優先度のルールを明確にする |
| 自動通知・割り振りの仕組みづくり | MAツールやCRMを活用し、リアルタイムで通知・自動アサイン |
| インサイドセールス部門の活用 | 専任チームで初動対応を行い、営業担当の負荷を軽減 |
| マーケティングとの連携強化 | ホットリードの判断基準を共有し、迅速に営業に連携する体制を整備 |
クロージングまでの流れに再現性がない
営業担当ごとに受注までの進め方や提案の切り口が異なると、組織としての営業力の底上げや成果の安定が難しくなります。
特に新人や中堅社員にとっては、成功パターンを再現できないことで成果が出しづらく、マネジメントや育成の観点でも大きな課題となりえます。
■ 問題点
- 営業ごとにアプローチや提案の質がバラバラで成果に差がある
- 属人的な手法に頼っており、チームとしてのノウハウが蓄積されない
- 効果的な進め方が共有されておらず、新人が成果を出しづらい
■ 要因・原因
- クロージングまでのプロセスが明文化されていない
- ヒアリング内容や提案資料のフォーマットが統一されていない
- ナレッジ共有の仕組みが整備されておらず、情報が属人化
- マネージャーが各担当の商談内容を十分に把握できていない
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| セールスプロセスの標準化 | ステージごとに必要なアクションや資料、チェック項目を明文化 |
| 商談記録・ヒアリング項目の統一 | CRMやSFAで必須項目を設定し、抜け漏れを防止 |
| 成功事例・失注事例の共有会 | クロージング成功・失敗の理由を定期的にチームで共有 |
| トークスクリプトや提案資料のテンプレ化 | 一定の品質を保った商談が誰でもできるよう仕組み化 |
| ロールプレイングの導入 | 再現性を高めるために、実際の商談を想定した練習機会を増やす |
営業メンバーごとに提案やクロージングの進め方が異なると、成果の再現性がなく、育成やチーム強化にも支障が出ます。属人化を防ぎ、営業力を底上げするための改善アプローチを解説した記事はこちらの記事をご覧ください。
マネジメント・評価に関する課題
営業マネジメントや評価制度に課題があると、組織全体のパフォーマンスや営業担当者のモチベーションに大きく影響します。
目標設定が曖昧だったり、成果や行動が適切に評価されなかったりすると、優秀な人材の離職や組織の成長停滞を招くリスクがあります。
- KPI・KGIに偏重し、行動評価が軽視されている
- 現場と乖離した目標設定でモチベーションが上がらない
- インセンティブ設計がチーム連携を阻害している
- 日報や週報が形式的で、実態把握につながっていない
- 会議が報告中心で、課題解決に結びついていない
KPI・KGIに偏重し、行動評価が軽視されている
成果数値(KPI・KGI)のみを重視する評価制度では、プロセスや努力が正当に評価されず、営業担当者のモチベーション低下や長期的な成長の阻害を招く恐れがあります。
特に若手や中堅層の育成においては、行動面の評価が欠かせません。
■ 問題点
- 数字での成果だけが評価対象となり、行動の質が無視される
- 営業担当者が短期的成果のみを追いがちになる
- 若手メンバーが評価されにくく、モチベーションを失いやすい
■ 要因・原因
- 評価基準がKPI・KGIの達成率のみに限定されている
- 行動やプロセスの可視化・記録が不十分
- マネージャーの観察やフィードバックの仕組みが整っていない
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| 行動指標の明確化 | アポイント件数、提案数、顧客フォロー数など具体的な行動KPIを設ける |
| 評価項目の多軸化 | 数値成果に加え、プロセス評価やチーム貢献度を含めた多角的評価を導入する |
| フィードバック文化の定着 | 日報や1on1面談を活用して、行動に対する具体的なフィードバックを行う |
| CRMやSFAの活用 | 営業活動のプロセスデータを可視化し、行動実績も管理できる環境を整備する |
成果数値だけを評価軸にしていませんか?KPI・KGIに偏重した評価制度では、プロセスや行動が正当に評価されず、若手や中堅の成長を阻害する恐れがあります。
行動評価を取り入れた仕組みづくりのヒントはこちらの記事をご覧ください。
営業目標はどのように設定すればいい?具体例や新人向け目標を紹介!
現場と乖離した目標設定でモチベーションが上がらない
現場の実情を無視した高すぎる、あるいは曖昧な目標設定は、営業担当者のやる気を削ぐ大きな要因となります。
特に達成可能性の低い数値目標や、根拠のない指標が一方的に与えられることで、組織全体の士気が低下し、離職にもつながりかねません。
■ 問題点
- 目標の達成が困難で、メンバーが挑戦意欲を持てない
- 目標の妥当性が理解されず、納得感がないまま業務を進めることになる
- 達成困難な目標が続くことで、離職や評価不信につながる
■ 要因・原因
- 現場の営業状況や顧客環境を加味せず、経営サイドが一方的に目標を設定している
- 過去実績や市場の変化が反映されていない定量設定
- 目標設定プロセスに現場の意見やデータが活用されていない
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| ボトムアップ式の目標設計 | 現場の実態をもとに、担当者やマネージャーからの意見を取り入れて目標を設定する |
| 実績データに基づいた設定 | 過去の実績・市場環境・営業リソースを踏まえた現実的な数値を目標とする |
| 中間目標や段階目標の導入 | 長期的なKGIに対して短期のKPIを細分化し、進捗を実感できる仕組みにする |
| 目標設定の透明化 | 目標設定の根拠や背景を丁寧に説明し、メンバーの納得感を高める |
インセンティブ設計がチーム連携を阻害している
営業の成果を促すためのインセンティブ制度は、本来であれば個人と組織の成長を促進する仕組みであるべきです。
しかし、個人の数値達成ばかりを重視した設計になっていると、チーム内での情報共有や協力体制が損なわれ、営業全体のパフォーマンスを逆に低下させるリスクがあります。
■ 問題点
- チーム内での情報共有が減り、属人的な営業活動が増える
- 部門をまたいだ連携(例:インサイドセールスやカスタマーサクセス)に協力が得られない
- 数値を優先しすぎた行動により、顧客満足や組織全体の目標が置き去りになる
■ 要因・原因
- 個人の売上や件数など短期成果のみに連動した報酬体系
- チーム成果や貢献度が評価・報酬に反映されない仕組み
- インセンティブの設計段階で、チームパフォーマンスの視点が抜け落ちている
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| チーム成果に基づく報酬設計 | チーム全体での目標達成や貢献度も評価軸に組み込み、連携を促す |
| クロスファンクショナル貢献の評価 | 他部門との協力や社内ナレッジ共有なども評価対象に含める |
| インセンティブ制度の見直し会議 | 現場を巻き込み、制度改善を定期的に行うことで納得感と効果を高める |
| 行動指標と成果指標の両立 | 顧客対応件数、フィードバック共有などの行動面も報酬設計に反映する |
日報や週報が形式的で、実態把握につながっていない
営業活動の進捗や現場の状況を把握するために導入される日報・週報。しかし、入力が目的化し「書くための日報」になってしまうと、マネジメントにとっても実態を把握する材料とはなりません。
その結果、課題発見や適切な指導ができず、組織全体の成長にも悪影響を及ぼします。
■ 問題点
- 営業の現場状況が正しく把握できず、的外れなマネジメントになる
- 本来の目的を果たさず、記録業務がただの負担となっている
- 課題の早期発見や成功パターンの共有が困難になる
■ 要因・原因
- フォーマットが目的不明確で、入力項目が多く形式的
- 記入内容が評価や査定に結びつかず、モチベーションが湧かない
- データの活用がされず、現場からのフィードバックがない
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| フォーマットの見直し | 「行動の記録」ではなく「気づき・改善点」を中心に設計し直す |
| 記入内容の活用 | 1on1やチームMTGなどで日報・週報を積極的に参照しフィードバックを行う |
| KPI連動や振り返りの習慣化 | 数値と現場の行動・気づきを紐付けて、継続的な改善に活かす |
| ツール化・音声入力等の効率化 | 業務負荷を下げることで、内容の質向上と継続率を両立させる |
会議が報告中心で、課題解決に結びついていない
営業会議やチームミーティングは、本来、課題の発見と解決、戦略のすり合わせの場であるべきです。しかし、実態としては「報告だけで終わる会議」になっているケースも少なくありません。
参加者の当事者意識や改善意欲が薄れ、組織としての学習と成長の機会を逸してしまいます。
■ 問題点
- 会議が単なる情報共有の場になり、問題解決や意思決定につながらない
- 参加者の発言が少なく、建設的な議論が生まれない
- 会議後にアクションが明確にならず、時間対効果が低い
■ 要因・原因
- アジェンダや目的が事前に明示されていない
- ファシリテーションの不在やスキル不足
- 課題の可視化や進捗のトラッキングが仕組み化されていない
- 会議体が習慣的に惰性で運営されている
■ 解決策
| 解決策 | 内容 |
|---|---|
| アジェンダの事前共有 | 会議の目的・ゴール・議題を事前に明示して参加意識を高める |
| 報告資料の事前提出 | 報告は資料に任せ、会議時間は議論・課題解決に集中 |
| ファシリテーターの配置 | 会議進行役を決めて発言の促進・軌道修正を行う |
| 課題ベースでの議論設計 | KPI乖離や現場課題に基づいたトピックで議論する習慣をつける |
| 会議ログ・アクションの明文化 | 会議の決定事項と担当・期限を明記して、確実に実行フェーズへ |
戦略・方針に関する課題
営業活動の土台となる戦略や方針が不明確だったり、現場との乖離が生じていたりすると、営業組織全体の動きがバラバラになり、成果の最大化が困難になります。
また、方向性の不一致はモチベーション低下や業務の非効率を招く要因にもなります。
- 顧客ニーズに合った営業手法が定まっていない
- ターゲット選定が場当たり的で一貫性がない
- 自社の強みが打ち出せず、価格競争に陥りがち
- 新規・既存営業のバランスが取れていない
- 単価やLTVを踏まえた営業設計ができていない
顧客ニーズに合った営業手法が定まっていない
顧客の購買行動や情報収集の手段が多様化するなか、画一的な営業手法では成果につながりにくくなっています。自社の商品・サービスがどのようなアプローチで最も響くのかが明確でないと、営業活動は非効率になり、顧客からの信頼獲得や成約にもつながりにくくなります。
■ 問題点
- 顧客に対して最適なアプローチ方法が分からず、試行錯誤が続く
- 営業メンバーごとにアプローチがバラバラで、再現性がない
- 営業活動の効果検証がしづらく、改善が進まない
■ 要因・原因
- 顧客セグメントごとのニーズ分析が不足している
- 過去の商談データや反応のフィードバックが活用されていない
- 営業手法の型(トークスクリプトやプロセス設計)が未整備
- マーケティング部門との連携が弱く、顧客理解が浅い
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 顧客属性ごとの営業手法の検証と標準化 | 業種・役職・課題ごとに最適な営業手法をテストし、再現性のある型を構築する |
| 顧客インサイトの可視化 | 商談内容やヒアリング結果をデータベース化し、傾向を全社で共有する |
| マーケティングと営業の情報連携の強化 | ペルソナ設計やカスタマージャーニーを共同で設計し、営業活動に反映する |
| 営業ナレッジの蓄積と活用 | 成功事例や失注理由を収集し、チーム全体で学習・改善する仕組みを整備する |
画一的な営業では通用しない時代、自社に最適な営業アプローチを見極められていますか?顧客ニーズに即した手法を定めることで、営業の再現性・成約率が大きく向上します。具体的な改善策はこちらの記事をご覧ください。
営業アプローチの方法とは?新規・既存攻略から効率化、打開策まで徹底解説
ターゲット選定が場当たり的で一貫性がない
営業活動の効率を高めるためには、明確なターゲット選定が不可欠です。
しかし、明確な基準や戦略がないまま場当たり的にアプローチ先を選定してしまうと、成約率が低下し、営業リソースの無駄遣いにつながります。全社で共有された「狙うべき顧客像」の明確化が重要です。
■ 問題点
- 営業が属人的な判断でターゲットを選定しており、成果にばらつきが出ている
- 顧客ニーズとのミスマッチにより、アプローチの効果が上がらない
- 顧客データが蓄積・活用されておらず、戦略が属人的になっている
■ 要因・原因
- 理想顧客像(ICP:Ideal Customer Profile)が定義されていない
- 過去の受注・失注データが分析されておらず、傾向が把握できていない
- ターゲット選定を判断する基準やフローが組織として明文化されていない
- マーケティング・営業・インサイドセールスの役割が分断されている
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| ICP(理想顧客像)の策定 | 過去の成功案件をもとに、業種・規模・課題・行動特性などの基準を定める |
| 過去データの分析とターゲット条件の明文化 | 受注率やLTVが高い顧客の共通点を抽出し、アプローチ優先順位を設ける |
| ターゲットリストの一元管理と定期更新 | 営業・マーケ・インサイドが共通のリストで活動し、定期的に精度を見直す |
| 選定基準の教育と浸透 | 営業現場へ選定ロジックやターゲット戦略の意図を共有し、属人性を排除する |
自社の強みが打ち出せず、価格競争に陥りがち
営業現場で「競合より安くします」といった価格訴求ばかりが前面に出てしまうケースは少なくありません。本来訴求すべき価値や強みが十分に伝わらないことで、顧客にとっての選定理由が「価格」だけになってしまい、営業が疲弊する原因にもなります。自社ならではの価値提案(バリュープロポジション)を整理・言語化し、営業全体で共有する必要があります。
■ 問題点
- 競合と差別化された提案ができず、価格競争に巻き込まれやすい
- 顧客が自社サービスの「価値」を理解できず、価格のみで判断される
- 営業担当ごとに訴求ポイントがバラバラで、一貫した提案ができていない
■ 要因・原因
- 自社サービスの強みや独自性が営業現場に十分に共有されていない
- 提案資料やトークスクリプトが競合比較や価格訴求に偏っている
- 顧客課題と自社サービスの結びつきを整理できていない
- 営業自身が「なぜこの価格なのか」を納得しておらず、説得力が弱い
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 自社の強み・差別化ポイントの整理 | 機能・導入効果・支援体制など、他社との比較で優位性がある点を明確にする |
| バリュープロポジションの言語化と社内共有 | 「顧客にとっての価値」をわかりやすく伝えるトーク・資料を標準化し共有 |
| ケース別提案ストーリーのテンプレート化 | 顧客課題に応じて提案の切り口を変えられるような営業ストーリーを準備 |
| 提案スキル向上のためのトレーニング実施 | 価格以外の価値訴求に自信を持てるよう、実践形式でのトレーニングを定期的に実施 |
価格競争に疲れていませんか?競合との差別化ができず、自社の価値が伝わらない営業は、成果にもつながりにくくなります。自社ならではの強みを言語化し、価格以外で選ばれる営業へ。解決策はこちらの記事をご覧ください。
【事例あり】ソリューション営業とは?違いや手法、適任な商材・人まで徹底解説
新規・既存営業のバランスが取れていない
営業組織では、新規開拓と既存顧客のフォローアップの両立が求められます。
しかし、目先の受注を追うあまり新規営業に偏ったり、逆に既存顧客の対応に追われて新規活動が疎かになったりと、バランスが崩れやすいのが現実です。どちらかに偏ると売上の安定性や成長性が損なわれるため、戦略的な営業活動の設計が必要です。
■ 問題点
- 新規開拓に偏りすぎて既存顧客のフォローが手薄になり、離反が増える
- 既存営業ばかりに注力して新規のパイプラインが枯渇する
- 営業担当者によって活動の方向性がバラバラで、組織としての一貫性がない
■ 要因・原因
- 営業KPIが新規または既存のどちらか一方に偏って設定されている
- 業務負荷やリソース配分に戦略的な設計がされていない
- 新規と既存で必要なスキルが異なり、適切な人員配置ができていない
- 上層部の指示や方針が曖昧なままで、現場が迷っている
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 新規・既存の比率を指標化し、バランスを定義 | 業種・商材ごとに適切な新規:既存比率を定め、KPIにも反映させる |
| 営業活動を2軸で可視化してモニタリング | どちらかに偏っていないかを定期的にデータで確認し、軌道修正を行う |
| 専任担当の配置や役割分担の見直し | スキルや業務特性に応じて新規・既存で分業または兼任体制を最適化 |
| 新規・既存営業それぞれの成功事例の共有 | 両者の営業ナレッジをチームで共有し、バランス良く成果を出せる体制をつくる |
単価やLTVを踏まえた営業設計ができていない
営業活動を効果的に行うためには、商材の単価や顧客のLTV(顧客生涯価値)を正しく把握し、それに基づいた戦略設計が欠かせません。
しかし実際の現場では、単価の高低やLTVに関係なく同じ手法やリソース配分で営業が進められているケースも多く、コスト対効果が合わない、成果が伸びないといった問題につながっています。
■ 問題点
- 低単価商材に高コストな営業手法をかけて赤字になる
- 高LTV商材に十分なリソースが割かれておらず、収益機会を逃している
- 営業活動が属人的で、費用対効果の視点が欠けている
■ 要因・原因
- 単価やLTVなどの経済性指標が営業現場に共有されていない
- 顧客の購買行動や継続傾向を分析する仕組みがない
- リード獲得〜クロージングまでの営業コストを可視化できていない
- 全顧客に対して画一的な営業プロセスを適用している
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 商材別に単価とLTVを明確にし、営業戦略と連動 | 単価とLTVに応じて、インサイドセールス・フィールドセールスなどを最適配置 |
| 営業チャネルごとのコストと効果を可視化 | どの手法がどの顧客に適しているかを、費用対効果で検証・改善 |
| 顧客タイプ別に営業プロセスを分岐させる | LTVや成約率に基づいてアプローチ方法を変え、効率化を図る |
| マーケ・営業・経営で指標を共有する仕組み構築 | LTVやCAC(顧客獲得コスト)を全体で共有し、組織的な判断を可能にする |
ツール・データ活用に関する課題
営業活動の高度化が進む中で、SFAやCRMなどのツール、蓄積された営業データをいかに有効活用できるかが、組織全体の生産性向上に直結します。
しかし、ツールの導入が形だけに終わっていたり、現場での定着が進まなかったりすることで、本来得られるはずの効果を十分に発揮できていない企業も少なくありません。
- SFA・CRMの運用が定着せず、活用できていない
- 蓄積されたデータが意思決定に使われていない
- デジタルツール導入の目的が共有されていない
- 営業リストの精度が低く、アプローチ効率が悪い
- 提案資料などの更新が追いつかず、手間がかかる
SFA・CRMの運用が定着せず、活用できていない
営業活動の効率化や可視化、ナレッジの蓄積においてSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)は欠かせない存在ですが、導入しただけで現場に定着せず、形だけの運用になってしまうケースも少なくありません。
こうした状態では情報の一元化が進まず、営業判断の質や業務効率にも悪影響を及ぼします。
■ 問題点
- データの入力漏れや未更新が多く、情報が信頼できない
- SFA/CRMを使うことが目的化し、活用されていない
- 経営判断や育成などにデータが活かされていない
■ 要因・原因
- 入力項目が多すぎて現場の負担になっている
- 使い方の教育が不十分で、活用のイメージが湧かない
- システム導入の目的やメリットが現場に伝わっていない
- マネージャー自身がツールを活用していない・評価指標に組み込まれていない
- 既存業務との整合性が取れていない(例えばExcelとの二重管理など)
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 入力項目の見直しと最小化 | 必要最低限の項目に絞ることで、現場の負担を軽減 |
| 利活用目的の周知と成功事例の共有 | 「入力がどう活用され、何につながるのか」を現場に伝え、納得感を醸成 |
| 初期研修+定期的なリマインド教育の実施 | 定着のためにOJTやマニュアルだけでなく、繰り返しの教育機会を設ける |
| マネジメント評価にSFA/CRMの活用度を反映 | 上司も積極的に使う体制を作り、活用を「組織文化」として根付かせる |
| 他ツールとの連携や自動化による負担軽減 | Excelやメールと連携するなどして手入力を最小限に抑える |
SFAやCRMを導入したのに現場で活用されていない――そんな悩みはありませんか?ツールの定着には、入力負担の軽減や活用目的の共有、教育体制の整備が不可欠です。形だけの運用を脱し、営業力を底上げするヒントはこちらの記事をご覧ください。
蓄積されたデータが意思決定に使われていない
営業活動においては、SFAやCRMなどを通じて多くのデータが蓄積されているものの、それが実際の意思決定や戦略立案に反映されていないケースがあります。
データドリブンな経営が実現されていないと、勘や経験に頼った判断が中心となり、再現性のある成果創出が困難になります。
■ 問題点
- 定性判断に頼ったマネジメントが続き、改善が属人的になる
- 収集したデータが活かされず、蓄積することが目的化している
- データに基づく分析や振り返りが行われていない
■ 要因・原因
- 必要なデータの定義が曖昧で、分析に活かせる形で整理されていない
- データを可視化・分析するスキルやツールが社内に不足している
- 「どのデータをどの意思決定に使うか」が明確に設計されていない
- 分析や報告が形式的で、アクションに結びついていない
- マネジメント層がデータ活用の重要性を理解していない、または軽視している
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 意思決定に必要な指標の定義と整理 | 活用すべきKPIや評価指標を明確化し、データ構造を見直す |
| ダッシュボードやレポートの自動化 | データをリアルタイムに見える化し、判断の材料に使いやすくする |
| データリテラシー向上のための研修・勉強会の実施 | マネージャーや現場担当者にデータの読み方・活用法を教育する |
| 分析からアクションにつなげるフレームを設計 | 「数値→原因→対策」の流れを習慣化し、振り返りの場を設ける |
| データを使った意思決定の事例共有 | 成果につながった活用事例を社内に展開し、活用の意義を浸透させる |
デジタルツール導入の目的が共有されていない
SFAやCRM、営業支援ツールなどのデジタルツールを導入しても、「なぜ使うのか」「何のために必要なのか」が現場に伝わっていなければ、定着は進まず、形だけの運用に終わってしまいます。
ツール導入の目的が社内で共有されていないと、使い方が属人化し、かえって非効率な業務が増える原因にもなり得ます。
■ 問題点
- ツールが使われず、形骸化してしまう
- 定着せず、現場の業務に負担だけが残る
- データが正しく蓄積されず、分析・活用ができない
■ 要因・原因
- 経営層・現場間でツール導入の目的や期待成果が共有されていない
- 導入が手段化し、業務課題との結びつきが不明確
- 現場にとってのメリットが伝わっておらず、当事者意識が薄い
- 「導入=現場任せ」になっており、フォロー体制が不十分
- 操作や導入プロセスに関する十分な教育・トレーニングがなされていない
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 導入目的・背景を明文化し、社内で共有 | なぜ導入するのか、どんな業務改善を目指すのかを資料や説明会で伝える |
| 現場の課題を起点としたツール選定 | 現場業務のどこをどう改善するかを明確にし、目的ベースで導入する |
| 部門横断でのプロジェクトチーム設置 | 営業・IT・マネジメントの連携体制を整備し、現場との橋渡しを担う |
| 現場ユーザー向けの導入メリット訴求 | 作業時間削減・成果向上などのメリットを具体的に示す |
| 操作教育と運用ルールのマニュアル化 | 使い方の統一と定着に向けて、ガイドラインや研修を実施する |
デジタルツールを導入しても、「なぜ使うのか」が現場に伝わらなければ形骸化してしまいます。導入目的や現場メリットを共有し、定着と活用を促すにはどうすればいいのか?その答えはこちらの記事をご覧ください。
【具体業務別】インサイドセールスツールのおすすめ18選!一式導入した際の費用例も徹底解説
営業リストの精度が低く、アプローチ効率が悪い
営業活動の出発点とも言える「営業リスト」の質が低いと、どれだけ努力しても成果にはつながりません。見込みの低いターゲットへのアプローチが増え、営業効率が著しく低下するほか、現場のモチベーション低下や組織全体のPDCAが回らない原因にもなり得ます。
■ 問題点
- リストにある企業・個人が見込み客でないケースが多く、無駄なアプローチが発生する
- 架電・メール配信などの工数ばかりがかかり、成約率が上がらない
- 営業現場が「リストの質」への不信感を持ち、ツールや仕組みを活用しなくなる
■ 要因・原因
- 適切なターゲティングがされていないままリストが作られている
- 古い情報や不正確なデータがリストに混在している
- リスト作成における明確な基準やセグメントの設計がされていない
- 営業とマーケティング間で連携がとれておらず、インサイトの共有が不足している
- 購入したリストをそのまま活用しており、検証・精査がされていない
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| ターゲット像を明確に定義し、条件を統一 | 業種・規模・課題・決裁者属性などを基に、見込み度の高い条件を設定 |
| リスト作成ルールの標準化 | 情報の取得元・更新タイミング・記載項目などを統一して整備 |
| SFA・CRMと連携して最新情報に基づく管理 | 過去の接点履歴や対応状況をもとにリストを随時更新・改善 |
| 営業・マーケティング間でのフィードバック連携 | リードの質・傾向を定期的に共有し、リスト改善に活かす |
| データクレンジングと見込み度スコアリングの実施 | 無効な情報を除去し、有望な顧客に優先順位をつける体制を整備 |
提案資料などの更新が追いつかず、手間がかかる
営業現場では日々の提案活動に多くの時間を費やしますが、提案資料や営業用スライドが古いまま使われていたり、都度修正が必要で非効率な状況に陥っている企業も少なくありません。
資料の更新遅れは、顧客への印象を損なうだけでなく、営業の生産性やモチベーションにも影響を与えます。
■ 問題点
- 社内の資料が最新情報に更新されておらず、誤情報を含んだまま使用される
- 営業担当者が都度、個別に資料を作り直すため、非効率で属人的になっている
- 情報の一元管理がされておらず、資料の検索や共有に時間がかかる
■ 要因・原因
- 資料更新の責任が不明確、または専任がいない
- ナレッジ共有の体制が整備されておらず、各営業が独自に資料を作成
- 社内における情報更新の優先度が低く、後回しになっている
- 営業部門とマーケティング・企画部門との連携不足
- 管理・配布プラットフォームが整備されていない
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 資料更新の担当者または専任チームの設置 | 情報更新の責任を明確化し、定期的な見直し体制を整備 |
| 資料テンプレートの整備と統一 | 営業全体で使える汎用テンプレートを整備し、無駄な個別対応を削減 |
| 社内ナレッジ共有ツールの導入 | スライドや資料を一元管理し、誰でも最新版にアクセスできる環境を構築 |
| マーケ・企画と営業で連携した情報更新 | プロダクトやサービスの最新情報を迅速に反映できる連携体制を構築 |
| 定期的なレビュー会の実施 | 提案資料の有用性・内容の鮮度を営業チームで共有・改善する文化を醸成 |
組織文化・風土に関する課題
営業組織の成果は、制度や戦略だけでなく、日々のコミュニケーションや働き方、評価のされ方といった「組織文化・風土」に大きく左右されます。
たとえ優れた施策を導入しても、現場に根付く価値観や雰囲気が変わらなければ、定着や改善は進みません。
- 営業部門が孤立し、他部門との連携が弱い
- 失敗を共有しづらく、ナレッジが蓄積されない
- 成果主義が行き過ぎ、不正や過剰営業の懸念がある
- 数字至上主義が強く、チームワークが損なわれている
- メンバーとマネージャー間の信頼関係が希薄
営業部門が孤立し、他部門との連携が弱い
営業部門が自部門のみで業務を完結させようとするあまり、マーケティングやカスタマーサクセス、開発部門など他部門との情報共有が不足してしまうケースがあります。
部門間連携が機能しないと、顧客ニーズの把握や商品改善の機会を逃し、結果的に営業活動の非効率化や顧客満足度の低下につながる恐れがあります。
■ 問題点
- 顧客フィードバックが商品開発やサービス改善に反映されにくい
- マーケティング施策と営業活動がかみ合わない
- サポート部門との情報連携がなく、顧客対応の質が低下する
- 組織全体での戦略立案やナレッジ共有が進まない
■ 要因・原因
- 組織構造上の縦割り体制により、部門横断の協働がしにくい
- KPIや目標が各部門で分断されており、連携する動機が薄い
- 部門間の定例会や連携ミーティングが存在しない
- 情報共有のための仕組みやツールが未整備
- 営業部門が「現場主義」で完結志向が強く、連携の意識が希薄
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 部門横断の定例ミーティングを設置 | 営業・マーケ・開発・CSなどで定期的に情報共有し、課題を共有 |
| 共通KPIや連携目標の設定 | 複数部門で達成を目指すKPIを設け、連携のインセンティブを生む |
| フィードバックループの整備 | 営業の現場情報をマーケや開発に届けるしくみ(ツールや報告フロー)を構築 |
| コミュニケーションツールの活用 | SlackやNotionなどで部門横断のチャネルをつくり、情報の壁をなくす |
| クロスファンクショナルチームの設置 | プロジェクト単位で各部門のメンバーが参画するチーム体制を構築 |
営業部門が他部門と連携できていないと、顧客対応の質や商品改善の機会を逃す原因になります。縦割り組織を打破し、部門間連携を強化するための実践的なポイントをこちらで解説しています
失敗を共有しづらく、ナレッジが蓄積されない
営業活動においては、成功事例だけでなく失敗から得られる学びも非常に重要です。
しかし、失敗の共有がネガティブに捉えられやすい文化では、個人の経験が組織に蓄積されず、同じミスを繰り返す原因となります。ナレッジが個人でとどまってしまえば、チーム全体の営業力向上にも限界が生じてしまいます。
■ 問題点
- 失敗が可視化されず、改善のための議論ができない
- 同じ失敗が複数人・複数チームで繰り返される
- ナレッジの蓄積・活用が個人任せで属人化する
- 失敗の報告が評価に悪影響を及ぼすと捉えられ、報告が抑制される
■ 要因・原因
- 失敗を責める文化・評価制度が存在している
- 失敗談を共有する仕組みや場が整備されていない
- 成功事例のみを表彰・可視化している
- ナレッジを記録・検索・活用する仕組み(ツール等)が不足している
- 営業担当が日々の業務に追われ、振り返る余裕がない
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 失敗事例を共有する場の定期開催 | 「失敗から学ぶ」目的の共有会を定期実施し、心理的安全性を確保する |
| 成功・失敗を問わず、挑戦を評価する文化醸成 | KPI未達でもプロセス・工夫を評価し、失敗共有がポジティブに受け取られるようにする |
| ナレッジ共有ツールの整備・運用 | 事例・トラブル・対処法を記録できるDBやWiki、Notionなどを導入・活用 |
| 成功事例と並列して「失敗からの学び」を表彰 | 表彰制度に「気づきを与えた失敗事例」などの部門賞を新設し、意識づけを図る |
| 営業日報や1on1での振り返り習慣化 | 失敗や気づきを振り返るフローを業務に組み込むことで、自然な情報蓄積を促す |
成果主義が行き過ぎ、不正や過剰営業の懸念がある
成果を重視する営業組織においては、数字を追う意識が強まる一方で、その過程や手段への配慮が軽視されるケースがあります。
行き過ぎた成果主義は、不正な受注や顧客への過剰なアプローチを生み、企業の信頼や長期的な成長を損ねかねません。健全な営業文化を築くには、「成果」だけでなく「プロセス」や「価値提供」にも目を向けたマネジメントが求められます。
■ 問題点
- 不正や誇張された報告、数字の操作が発生するリスク
- 顧客との信頼関係を損なう強引な営業や過剰なアプローチの横行
- 短期成果に偏った営業活動により、長期的な顧客育成が後回しになる
- 正しく誠実な営業が報われず、組織の価値観がゆがむ
■ 要因・原因
- 売上や契約数などの成果指標のみが評価対象になっている
- 行動プロセスや顧客満足が評価に反映されていない
- 目標未達が評価や報酬に直結し、心理的な追い込みにつながっている
- 不正・過剰営業へのチェック機能が不十分
- 営業倫理やコンプライアンスに関する教育が不徹底
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| プロセス評価の導入 | 行動量や顧客対応品質、改善努力などを評価指標に加える |
| 営業倫理・コンプライアンス研修の定期実施 | 不正・過剰営業のリスクや長期的悪影響を理解させる教育の機会を提供 |
| フィードバック付き1on1の実施 | 結果だけでなく取り組み姿勢や考え方を上司が確認・指導する場を定例化する |
| 失注・クレームのモニタリング強化 | 不自然な失注率や顧客トラブルの増加をアラートとして捉え、早期是正につなげる |
| 営業ルール・行動規範の明文化と社内周知 | 強引・過剰な営業のNG例を具体的に明記し、共通認識として浸透させる |
数字至上主義が強く、チームワークが損なわれている
営業成績の数値ばかりが重視される組織では、メンバー間の協力や支え合いといったチームワークが軽視されがちです。個人の成果ばかりが評価される環境は、助け合いをためらわせ、情報共有やノウハウの蓄積を妨げる要因となります。
営業組織としての総合力を高めるには、チーム単位の評価や共通目標の設定による一体感の醸成が求められます。
■ 問題点
- 情報共有が行われず、営業ノウハウが個人に閉じてしまう
- チーム間でのサポートや協力が起きづらく、孤立感が強まる
- 成果を上げた人だけが評価され、過程や貢献が無視される
- 競争意識が強くなりすぎ、健全な関係性や組織の一体感が失われる
■ 要因・原因
- 個人の数字(売上、契約数)のみで評価が行われている
- チーム単位での目標や評価指標が存在しない
- 情報共有や後輩指導などの行動が評価に反映されない
- リーダーや管理職によるチームワーク促進の働きかけが不足している
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| チーム目標や部門目標の設定と共有 | 個人ではなくチームで成果を追う文化を醸成する |
| 情報共有やサポート行動を評価指標に加える | ナレッジ提供やチーム貢献を定量・定性の両面で評価 |
| 成果とプロセスの両面評価制度を構築 | 数字だけでなく、取り組み姿勢や連携行動も評価対象とする |
| 営業会議での成功事例・失敗事例のチーム共有 | 他者から学ぶ文化を形成し、連帯感と成長意識を促進 |
| チームビルディング施策の実施 | ワークショップや懇親機会を通じて関係構築を促し、心理的安全性を高める |
メンバーとマネージャー間の信頼関係が希薄
営業組織において、マネージャーとメンバーの信頼関係は、パフォーマンスや定着率に大きく影響します。信頼が築かれていない環境では、メンバーが悩みや課題を共有できず、マネージャーも正確な状況把握や的確な支援が困難になります。結果として、チーム全体の成果や成長の阻害要因となりかねません。
結果として、チーム全体の成果や成長の阻害要因となりかねません。
■ 問題点
- メンバーが本音を言えず、課題が表面化しにくい
- フィードバックが一方通行で、納得感や成長実感が乏しい
- 上司への報告・相談が形骸化し、形だけのコミュニケーションに陥る
- 離職やモチベーション低下につながる
■ 要因・原因
- 目標達成プレッシャーや指示命令が強すぎ、対話が不足している
- 面談や1on1の質が低く、信頼構築につながっていない
- マネージャーに育成や共感の視点が欠けている
- メンバーの成長や努力が適切に認知・評価されていない
■ 解決策
| 解決策の内容 | 説明 |
|---|---|
| 定期的な1on1ミーティングの実施 | 業務だけでなく感情面やキャリアの話も含め、信頼構築の場とする |
| 傾聴と共感を重視したマネジメント研修の実施 | マネージャーに対話スキルと育成意識を持たせる |
| 成果以外のプロセスや行動への承認・称賛を行う | メンバーの努力を見逃さず、信頼される存在としての立場を築く |
| フィードバックの双方向化 | メンバーからマネージャーへのフィードバック機会も設け、対等な関係を促進 |
| 組織内での成功体験・失敗体験の共有文化を醸成 | 心理的安全性を高め、安心して本音が言える環境を整える |
外部環境に関する課題
営業活動は自社の努力だけでは完結せず、市場動向や競合の動き、顧客ニーズの変化など、外部環境の影響を大きく受けます。
社会情勢の変化や法規制の改正、テクノロジーの進化も、営業戦略やオペレーションに見直しを迫る要因となります。
- 市場変化で従来の営業手法が通用しなくなっている
- 顧客の購買行動が変わり、情報提供型営業が必要に
- 商材の認知度が低く、教育に手間がかかる
- 業界規制や法改正により営業活動が制限されている
- 業種や地域によって反応が異なり、標準化が難しい
市場変化で従来の営業手法が通用しなくなっている
近年、テクノロジーの進化や購買行動の変化により、これまで成果を上げていた営業手法が通用しなくなるケースが増えています。
従来の方法に固執すると、変化する市場に対応できず、機会損失や競争力の低下を招く恐れがあります。
■ 問題点
- 旧来の営業手法では顧客に響かず、受注率が低下している
- デジタルシフトに乗り遅れ、競合と比較されやすくなる
- 新しい営業施策への適応が遅れ、組織全体が保守的になる
■ 要因・原因
- 顧客の購買プロセスが変化している(例:オンライン情報収集の増加)
- デジタル活用に関する知見や体制が整っていない
- 営業現場が過去の成功体験から抜け出せない
- マーケティング部門との連携が弱く、顧客インサイトが得られていない
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| 営業プロセスの見直し | 顧客の購買行動に合わせて、非対面営業やインサイドセールスを取り入れる |
| デジタルツールの導入・活用 | MA(マーケティングオートメーション)やSFAを活用し、顧客接点を可視化・最適化する |
| 営業とマーケの連携強化 | 顧客ニーズを把握するために、マーケティング部門と情報共有を密に行う |
| 教育・研修の強化 | デジタルや新手法に関する知識を習得できるよう、継続的な学習機会を設ける |
従来の営業手法が通用しにくくなっている今、変化に対応できなければ機会損失や競争力低下を招きかねません。これからの時代に必要な営業アプローチの見直しポイントを、以下の記事で詳しく解説しています。
営業アプローチの方法とは?新規・既存攻略から効率化、打開策まで徹底解説
顧客の購買行動が変わり、情報提供型営業が必要に
顧客は営業を受ける前に自ら情報収集を行い、購買の意思決定をほぼ固めているケースが増えています。そのため、従来の「売り込み型」の営業ではなく、価値ある情報を提供し信頼を築く「情報提供型営業」への転換が求められています。
■ 問題点
- 商談の初期段階で顧客に「検討済み」と断られる
- 提案の説得力が弱く、価格や機能比較で劣勢になる
- 営業担当者が顧客のニーズを引き出せず、的外れな提案に終わる
■ 要因・原因
- 顧客が営業を受ける前に自ら情報収集をしている(インバウンド型購買行動)
- 営業が単なる製品説明にとどまり、価値訴求ができていない
- 顧客課題や業界動向を理解するための教育・情報共有体制が不十分
- マーケティングと連携したコンテンツ提供やインサイトの共有がされていない
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| 情報提供型営業への転換 | 顧客の課題に応じた業界トレンド・活用事例など、価値ある情報を発信する |
| 顧客理解力の強化 | 業界別ニーズやペルソナ理解を深める研修・教育を実施する |
| コンテンツ活用の推進 | 提案資料やホワイトペーパーなどを営業活動で活用し、信頼を獲得する |
| マーケティングとの連携 | コンテンツの企画・活用状況を共有し、顧客フェーズに応じた提案を可能にする |
商材の認知度が低く、教育に手間がかかる
新規性の高いサービスやニッチな市場をターゲットとする場合、顧客に対する「商材の説明」や「価値訴求」に多くの時間と労力がかかります。結果として、商談の歩留まりが悪化し、営業効率が著しく低下するケースも少なくありません。
■ 問題点
- 商談の大半が「説明」に終始し、本質的な提案に進まない
- 顧客が導入の必要性を感じにくく、検討フェーズまで進みにくい
- 営業メンバー間で訴求ポイントにばらつきが生まれ、成果に差が出る
■ 要因・原因
- 商材の市場認知度が低く、顧客が前提知識を持っていない
- 商材のメリット・活用法が複雑で、言語化が難しい
- 標準化された訴求ストーリーや資料が不足している
- 顧客の業界・業種によって説明の切り口が大きく異なる
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| トークスクリプト・訴求ストーリーの整備 | 顧客の検討段階に応じた営業トークや説明資料を標準化する |
| 顧客事例・ユースケースの共有 | 業界別の導入事例を整理し、顧客に近い成功体験として提示する |
| 教育コンテンツの活用 | ホワイトペーパーや解説動画などを使って顧客の理解を支援する |
| 社内ナレッジ共有体制の構築 | 効果的な説明・アプローチのノウハウをメンバー間で共有する |
業界規制や法改正により営業活動が制限されている
営業活動に関わる法規制には、特定商取引法、景品表示法、個人情報保護法、電気通信事業法、下請法など多岐にわたる法律が存在し、年々厳格化しています。
例えば特定商取引法では電話勧誘販売の際、オプトアウト対応や不実告知の禁止が課され、違反時には行政処分や罰金リスクがあります。また、個人情報保護法の改正によりリード情報の収集・管理方法の見直しが求められるなど、法制度対応の遅れが営業機会損失につながるケースも増えています。
■ 問題点
- 従来の営業手法(電話勧誘・飛び込み等)が規制に抵触するリスクがある
- 法令違反により、ブランド毀損・行政指導・罰金などの事態に発展する可能性
- 営業メンバーが何を「してよいのか・いけないのか」を把握できていない
■ 要因・原因
- 法改正・規制内容に対する社内の情報キャッチ体制が弱い
- 営業方針やマニュアルが古いままで、実態と乖離している
- 法務部門や管理部門との連携不足により、判断が属人的になっている
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| 法規制への対応方針を明文化・共有 | 営業マニュアルを最新化し、やってよいこと/NG行為を明確にする |
| 社内研修の実施 | 法改正や業界ルールに関する定期的な教育を実施し、全員の認識を統一する |
| 管理部門との連携強化 | 法務・コンプライアンス部門と連携し、事前確認や相談のフローを整備する |
| デジタルチャネルの活用 | 制限の少ない手法(インサイドセールス、コンテンツマーケティング等)に切り替える |
業種や地域によって反応が異なり、標準化が難しい
営業活動は、対象となる業種や地域によって商習慣や反応が大きく異なります。
そのため、画一的な営業手法では成果が出にくく、現場での対応が属人化しがちです。営業活動の再現性を高めるには、標準化と柔軟なカスタマイズのバランスが求められます。
■ 問題点
- 統一した営業プロセスが機能せず、属人性が高まる
- 営業手法の再現性が低く、新人育成や業績予測が困難になる
- 地域や業種特有の事情が把握されず、顧客との信頼関係が築きにくい
■ 要因・原因
- 業界ごと、地域ごとの違いを整理・分析できていない
- 営業現場からのフィードバックが収集・反映されていない
- 本社主導での一律な施策が現場にマッチしていない
■ 解決策
| 対策内容 | 詳細 |
|---|---|
| ターゲット別の営業パターンを策定 | 業種・地域別に効果的なトークスクリプトや提案資料を用意し、柔軟に活用できるようにする |
| 営業現場との定期的な意見交換 | 各エリア・業界の特性を現場からヒアリングし、施策に反映する体制を構築する |
| SFA等を用いたデータ分析 | 顧客属性ごとの反応傾向を蓄積・可視化し、仮説検証のサイクルを回す |
| コア部分だけを標準化 | 営業の基本フローのみを統一し、それ以外は現場の裁量で調整可能とする |
次に起こりうる営業課題の見つけ方
営業課題は、常に「いま困っていること」だけでなく、「これから起こるかもしれない問題」にも目を向ける必要があります。目の前の業務に追われがちな現場だからこそ、将来的な課題の兆しをいち早く捉え、先回りして対処することが、強い営業組織づくりの鍵となります。
- 営業課題の種類を体系的に把握する
- フレームワークを使って「次に起こる課題」を予測する
- 現場データと対話で“兆し”を拾う
営業課題の種類を体系的に把握する
営業課題は、思いつきや感覚で捉えるだけでは本質を見失いやすくなります。
まずは、営業課題を以下のようなカテゴリで分類・整理し、自社の現在地を俯瞰して把握することが重要です。
【組織設計】例:役割分担が曖昧/業務の属人化
【人材・マネジメント】例:育成が属人的/目標が納得されていない
【プロセス・オペレーション】例:SFA運用が定着しない/商談漏れが多い
【ツール・データ活用】例:蓄積データが意思決定に使われない
【市場・顧客変化】例:営業手法が通用しない/顧客の購買行動が変化
このような視点で全体像を整理することで、「今は問題化していないが、将来的に発生しそうな領域」が浮かび上がってきます。
フレームワークを使って「次に起こる課題」を予測する
次に起こる課題を予測するには、現場の変化を捉える観察力と、変化から因果関係を読み解く思考力が必要です。そこで有効なのが、以下のようなフレームワークです。
5W1Hで現場の変化を観察
現場の課題を早期に察知するためには、「なぜ成果が出なくなっているのか」を感覚ではなく、具体的な変化として捉える必要があります。そこで有効なのが、5W1Hのフレームワークです。
- Who(誰が):営業メンバー・顧客・マネージャーなど、関係者の変化
- What(何を):業務内容・成果物・目標指標などの変化
- When(いつ):業務のタイミング・商談スピードの変化
- Where(どこで):営業チャネル・顧客接点の変化
- Why(なぜ):変化の背景にある原因・外的要因
- How(どのように):業務プロセス・使っているツールの変化
このように6つの観点で「以前と比べてどう変わったか」を整理すると、今の問題・今後の問題の芽が見えてきます。
課題進行モデル(兆し → 軽症 → 重症)
課題は、いきなり深刻な問題として現れるのではなく、徐々に進行していく傾向があります。
| フェーズ | 状態の特徴 | 対処可能性 |
|---|---|---|
| 兆し | 一部の現場で違和感や変化が出始める | 高(未然に防げる) |
| 軽症 | 数値や結果に小さな影響が出始める | 中(プロセス修正が必要) |
| 重症 | 組織全体に大きな問題として顕在化 | 低(抜本的改革が必要) |
この進行モデルを意識することで、まだ“兆し”の段階で手を打つことができます。
現場データと対話で“兆し”を拾う
数値と会話の両面から「違和感」をすくい上げることが、課題予測の第一歩です。
SFAやCRMの数値データを観察する
→アポ率の急落/提案回数の偏り/成約スピードの変化 など
1on1や定例MTGで現場の声を拾う →「最近、●●しづらくなった」「●●が通じなくなった」といった発言
サイレントな兆候に注目する →進捗報告が減る/報告の間違えが増える/入力が遅れる/Slackや会話の温度感が変わる/勤退や生活態度に変化が現れる
こうしたデータと対話を掛け合わせることで、「数値には出ないが、放っておくと問題になりそうな予兆」を発見できます。
営業代行で解決できる営業課題ランキングTOP5
営業代行は「課題解決の選択肢」として、単なるリソース補完にとどまらない価値を持ちます。特に「専門性」「効率性」「即効性」といった観点から、一定の営業課題に対して非常に効果的な解決策となり得ます。
ここでは、営業代行を活用することで解決しやすい課題をランキング形式で紹介します。
自社が抱える課題が含まれていないかを確認しながら、自社にとって最適な代行の活用方法を検討する手がかりにしてください。
第1位:新規開拓が進まない/アポが取れない
第2位:営業人材が不足していて、機会損失が起きている
第3位:顧客フォローが属人化しており、案件管理が不安定
第4位:営業ノウハウ・トークスクリプトが蓄積されない
第5位:新規事業・新商品に営業リソースを割けない
第1位:新規開拓が進まない/アポが取れない
「新規開拓が進まない」「アポイントが思うように取れない」
こうした悩みは、あらゆる業種・業界の営業現場で頻出する代表的な営業課題です。
背景には、ターゲットリストの不備、架電数の不足、トークスキルのばらつきなど、複数のボトルネックが存在します。こうした状況に対し、営業代行の活用は“即効性”のある打ち手となり得ます。
【課題の背景】
新規開拓がうまく進まない背景には、「営業リストが不足している」「架電数が足りない」「トークスキルにばらつきがある」など、複数の要因が絡んでいます。特にBtoB営業においては、成果が出るまで一定の接触量が必要なため、リソースが足りないと成果も出づらくなります。
【代行の効果】
テレアポ代行やインサイドセールス代行を活用することで、限られた時間と社内リソースでは難しい大量アプローチが可能になります。
プロのオペレーターによる効率的な架電と、効果の高いスクリプトの活用により、即効性のあるアポイント獲得が期待できます。
【おすすめ代行タイプ】
・テレアポ特化型
・BtoB向け新規開拓専門代行
【活用事例】
大手企業向けコンサルティングサービスの新規開拓支援において、経営企画部門をターゲットにアウトバウンド施策(BDR)を実施。
アポイント獲得実績がほぼゼロだった状態から、月間9件のアポ獲得に成功し、4,000億円超の企業からも商談を獲得。
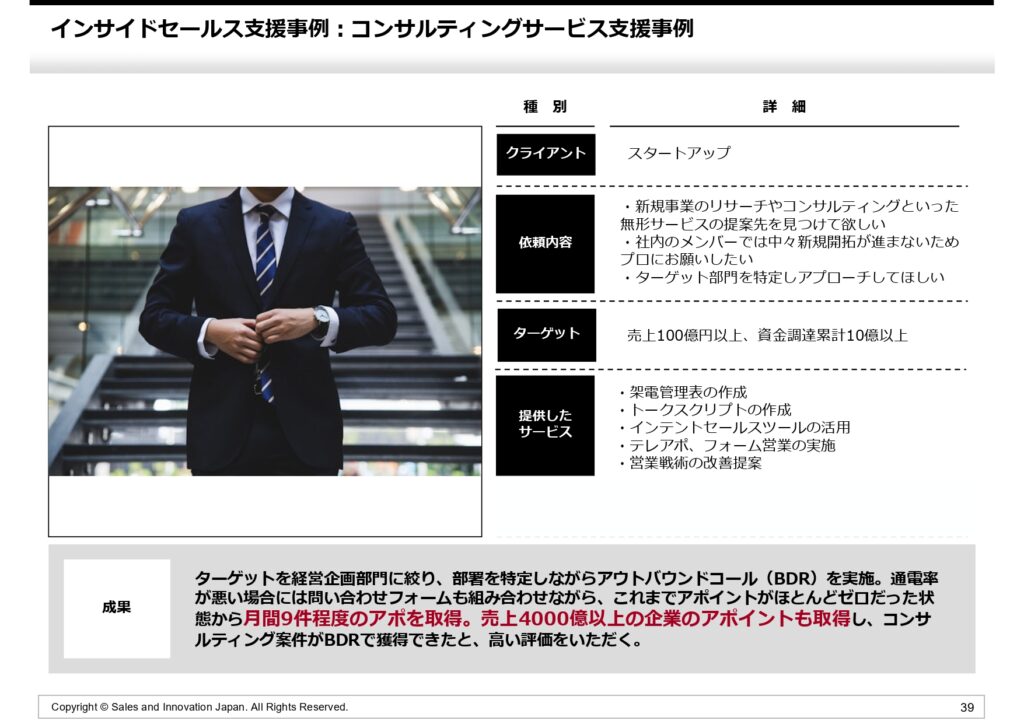
第2位:営業人材が不足していて、機会損失が起きている
営業リソースの不足は受注機会を逃す最も深刻な営業課題の一つです。採用難や育成リソースの不足、さらには離職率の高さといった要因により、せっかくの見込み顧客にアプローチできない企業も少なくありません。
特に展示会やセミナーなどで獲得したリードに対して即時に対応できなければ、せっかくの関心が薄れ、競合に流れてしまうことも。即戦力の営業人材を外部から確保し、スピーディーかつ確実に商談機会をつくることで、機会損失を最小化できます。
【課題の背景】
営業人材の採用難や育成リソースの不足、離職率の高さは、多くの企業で共通する悩みです。特に人手が足りない状況では、せっかくの見込み顧客をフォローできず、商談の機会損失が発生します。
【代行の効果】
即戦力となる営業人材をアウトソーシングすることで、社内で採用や教育に時間をかけることなく、営業活動を加速できます。
【おすすめ代行タイプ】
・常駐型のフィールドセールス代行
・業界特化型の営業代行
【活用事例】
インターネットサービス企業が、クリエイターネットワークを活用したギャラリー検索サイト立ち上げにあたり、営業ノウハウ不足を補うために営業代行を依頼。
Sales and Innovation Japanは、ターゲットリストの選定から飛び込み営業、提案資料やキャンペーン施策の改善提案など一連の営業活動を提供。
結果、わずか2週間で10件の有料会員を獲得し、現在では347件以上の掲載数を誇る業界トップクラスのサービスへと成長した。
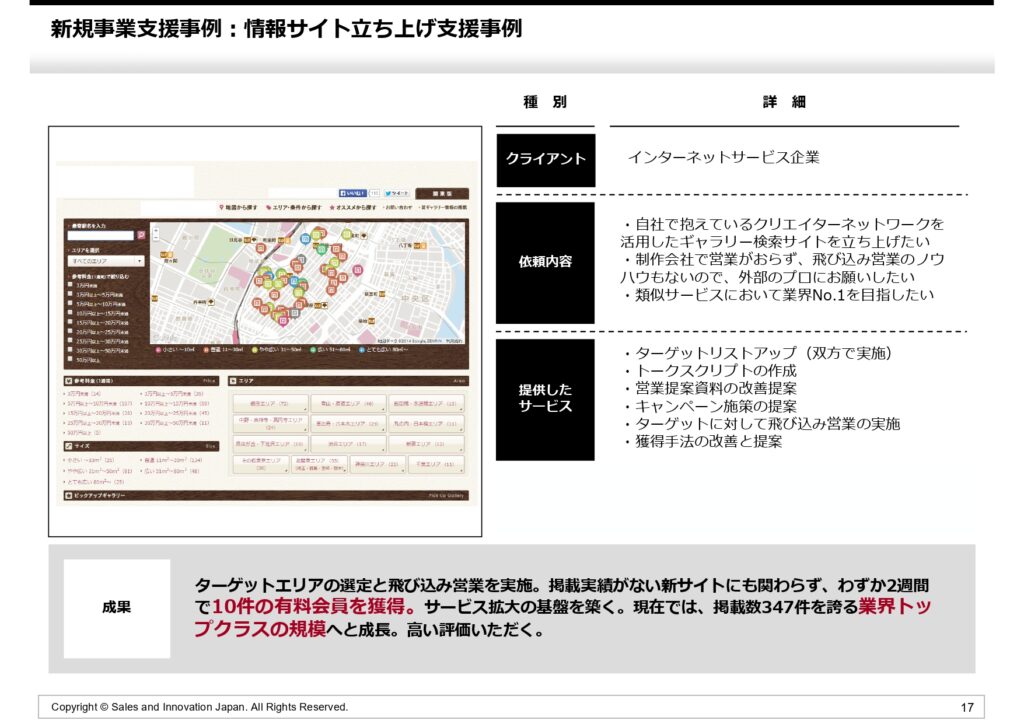
第3位:顧客フォローが属人化しており、案件管理が不安定
営業活動において、顧客フォローが特定の担当者に依存している状態は大きなリスクです。SFAやCRMの活用が不十分なまま、進捗や対応履歴が属人的に管理されていると、引き継ぎミスやフォロー漏れが発生しやすくなります。
結果としてホットな商談機会を逃したり、顧客満足度の低下を招くことも。仕組みに基づいた一貫した対応で属人性を排除し、安定した案件管理と成果の最大化が期待できます。
【課題の背景】
営業担当者ごとに進め方が異なり、SFA(営業支援システム)が未整備な場合、顧客対応が属人化しがちです。その結果、進捗の見える化が難しく、ホットリードの取りこぼしや案件漏れのリスクが高まります。
【代行の効果】
営業プロセスの設計から実行までを一括で外部に委託することで、標準化された対応が可能になり、案件管理の安定化につながります。
【おすすめ代行タイプ】
・SFA連携型のインサイドセールス代行
【活用事例】
既存顧客のフォローに工数がかかり新規開拓が滞っていたスタートアップ企業に対し、インサイドセールス支援としてトークスクリプト作成やテレアポ実施を行いました。アポ品質の高さが評価され、商談初週で即受注に成功しました。従来の営業代行会社より成果が良く、継続的なアポ確保体制の構築に貢献しました。

第4位:営業ノウハウ・トークスクリプトが蓄積されない
営業活動がOJTや個々の経験に依存していると、トークや提案の質にばらつきが生まれ、組織としての再現性や改善が難しくなります。「優秀な営業が辞めたらノウハウも消えた」といった事態も少なくありません。
トークスクリプトや提案手法の体系化ができていない場合、成果の安定化や若手の早期戦力化も阻まれます。こうした課題に対しては、スクリプト提供型の営業代行を活用することで、実績に裏打ちされたトーク設計や改善ノウハウを取り入れ、自社内に蓄積・定着させていくことが可能です。
【課題の背景】
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に頼った営業育成や、担当者任せの提案活動では、ノウハウが属人的になりがちです。結果として、成果の再現性がなく、改善サイクルが機能しません。
【代行の効果】
営業代行会社が保有する多種多様なスクリプトやノウハウを活用することで、自社にない知見を取り入れた効率的な営業活動が可能になります。蓄積された知見をもとに、改善や標準化も実現しやすくなります。
【おすすめ代行タイプ】
・スクリプト提供型営業代行
・ナレッジ共有型営業代行
【活用事例】
新商品でのシェア拡大を目指す装花・園芸サービス企業に対し、テレアポから訪問営業、資料改善支援までを実施。営業開始1週間で12件のアポイントを獲得し、潜在ニーズの発掘と見込み顧客の獲得に成功しました。さらに、営業活動で得たKBFを共有し、社内営業メンバーの意欲向上にも寄与しました。

第5位:新規事業・新商品に営業リソースを割けない
新規事業や新商品の立ち上げ時は、仮説検証やターゲットの見極めなど不確定要素が多く、営業リソースの投下をためらってしまいがちです。既存事業で手一杯な状態では、新たな挑戦に十分なリソースを割けず、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうこともあります。こうした局面では、短期集中型や新商材に特化した営業代行を活用することで、市場の初期反応をスピーディーにテスト可能。リスクを最小限に抑えながら、確度の高い商談機会の創出や方向性の検証を行えます。
【課題の背景】
既存事業で営業担当が手一杯な中、新規事業や新商品に対応する余力がない企業は多く見られます。また、仮説検証段階での営業投入にはリスクが伴うため、社内では優先順位が下がりがちです。
【代行の効果】
営業代行を活用すれば、短期間・小規模でのトライアル営業が可能になります。市場の反応を確かめたうえで、本格展開の判断ができるため、リスクを抑えた形での仮説検証が実現します。
【おすすめ代行タイプ】
・短期特化型の営業代行
・新商材専用チーム立ち上げ型
【活用事例】
BtoB通販企業の新規事業に対し、営業ノウハウの構築とテレアポ・トレーニング支援を実施。開始3ヶ月で社内売上ランキング1〜3位を独占し、営業手法の体系化によって大手企業からの問い合わせや売上が大幅に増加しました。購買率も12%から50〜60%に向上し、インサイドセールス組織の立ち上げにも成功しました。
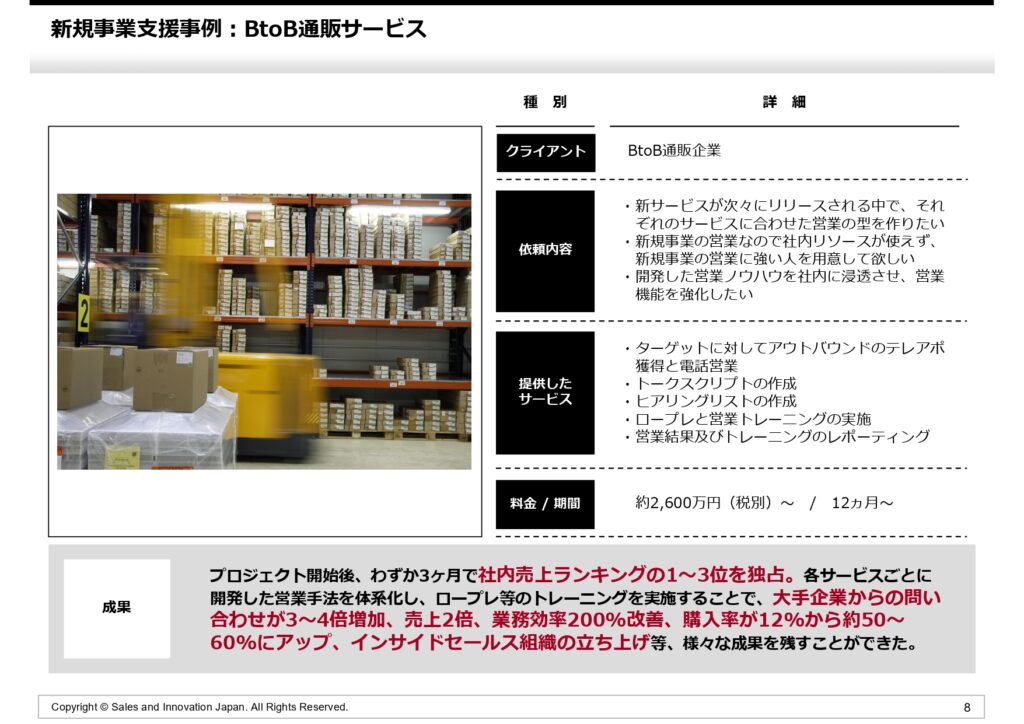
まとめ
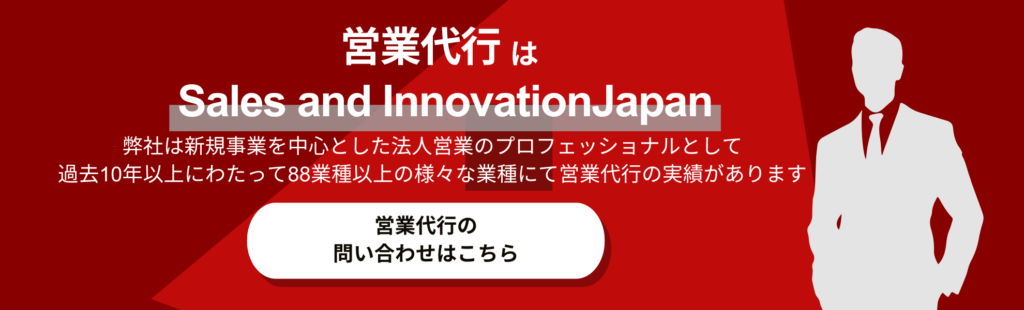
営業組織の課題は属人化や非効率にとどまらず、体制や評価、ツールの運用など多岐にわたります。こうした構造的な問題に向き合うには、自社の営業を客観的に見直すことが欠かせません。
しかし、日々の業務の中で課題を整理し、改善まで進めるのは容易ではありません。
この問題を解決するために、専門性と再現性を持つ営業代行を活用する企業が増えています。
自社の営業組織をどう変えていくべきか悩んでいる方は、まずは他社の支援事例からヒントを得てみてください。
営業支援の実績や具体的な導入事例は、こちらのページからご覧いただけます。
https://www.salesandinnovation.jp/results
また、営業課題の可視化や改善のご相談も随時受け付けておりますので、ご興味があればぜひお気軽にお問い合わせください。


入社2年間営業チームでtoB,toC向け商材の営業を行う。
その後、バックオフィスとして10年以上営業以外全てのサポート業務に従事し、
多数の営業パーソンの起業独立にも携わる。
その他にもマーケティングやリクルーティングも兼任。

